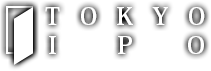東京IPO特別コラム:「ウクライナでの地上と地下を巡る戦い」
〜語られないものを視る眼〜
「ウクライナでの地上と地下を巡る戦い」
昨今のウクライナ情勢は、安全保障とエネルギーという2つの視点から見ないと全体像が見えません。
安全保障の観点
日本のメディアはロシアを悪者のように仕立てていますが、それは視点をどこから始めるかによります。ソ連崩壊前夜から欧米のリーダーたちはゴルバチョフ政権に東ドイツより東へはNATO(北大西洋条約機構)は拡大しないと約束していました。しかし、実際にはNATOははるか東へ拡大し、元々ロシア嫌いのバルト三国、ポーランドはもちろん、旧ユーゴ、ブルガリア等にまで広がりました。プーチン大統領がいうように、「約束は反故にされた」のでした。ロシアからすれば、ソ連時代の衛星国はおろかソ連を形成していた国にまで西欧側に巻き取られれば、不安を覚えるのは当然の話です。
今、ロシアの南西に位置し、直接国境を接するウクライナにまで欧米は接近しています。そのため、ロシアはウクライナ国境付近に約10万もの軍を集結させ、欧米にはNATOの拡大をやめてほしいと主張しています。一方、NATO側は拡大方針をやめる気はないと発表しています。よって、両者は平行線のままであるというのが現状です。
このように考えれば、プーチン大統領の言い分に分があり、NATOがウクライナの加盟を認めない代わりに、ロシアがウクライナ国境に集結しているロシア軍を撤退させることで妥結できるように思われます。
しかし、欧米は妥協に向けた姿勢を見せません。さらに、今月バイデン大統領は、ロシアはウクライナ侵攻をするだろうとの見解を示し、その行為の代償は高いと発言しました。このような物言いは、恐ろしく不自然です。本当に侵攻してほしくないなら、わざわざ侵攻するだろうと言わないはずです。いつものバイデン失言癖かで済ませない場面です。
目くらまし戦術?
バイデン大統領の強硬姿勢の裏には何があるのでしょう?よくあることとして考えられるのは、目くらまし戦術です。過去の失策等から世論の眼をそらすために、新しい危機を作り上げ、ヒーローを演じる戦術です。不人気の大統領が大きな選挙前によくやる戦術です。例えば、ブッシュ(子)政権によるイラク戦争があります。この戦争開始も2003年3月、中間選挙の年でした。3月という時期も2,3か月で勝利宣言できると見越し、夏の党大会で大いに盛り上がり、その余韻で11月の選挙を制する計画だったでしょう。
さて、今年も中間選挙の年ですが、バイデン大統領は不人気です。直近の調査では40%(中には30%台という報道も)に落ちています。第一の理由は、コロナ禍がなかなか収束できないことでしょう。特に直近ではワクチン接種証明と検査の義務化に反発する州(共和党系に多い)が声を大きく上げており、収拾がつく気配がありません。第二に、経済・景気対策ですが、脱炭素、社会インフラへの再投資等未来への投資を指向した政策ですが、大きな炭鉱を選挙区に持つ、身内の上院議員(民主)が妨害工作に出る等により議会でもめ続け、大きく2つに分割してそれぞれ攻防戦を繰り広げていますが、法案成立の目途は立っていません。第三に、インフレ苦があります。トランプ政権であれだけ金融緩和と紙幣増刷を繰り返せば当然な話なのですが、ようやく遅ればせながらテーパリングに引き続き、金利引き上げ検討のニュースが出てきました。(但し、スタグフレーションの懸念はありますが。。。)
このバイデン政権は、対策そのものは決して悪くないのですが、物事を進める推進力に欠けるのがイタイです。確かにバイデン氏のせいではない要素が多分にあるのは事実ですが、それだけに、今風な言葉だと、「自分ごと」として捉え、しっかり「汗をかかない」あるいは「かいていないように見えない」というのでしょうか。
とはいえ、議会との駆け引きを含め、これらは多分に民主主義制度の宿命です。例えば、オバマ大統領も第一期の選挙公約の目玉であった、いわゆるオバマケア法案(国民皆保険制度法)成立時には議会は大揺れに揺れていました。元々上院議員を1期しか務めていないオバマ大統領は、当初バイデン副大統領の議会工作力を期待し、あまり運動している風はなかったのですが、廃案の気運が高まる頃には、自らの政治生命を賭し議会工作を活発に行い、ようやく成立にこぎつけました。機能不全な議会のせいとして、知らん顔ばかりしていてはいけないのです。
しかし、ワシントン政治の裏を知りすぎているせいか、バイデン政権は今回目くらまし戦術に逃げてしまったのでしょうか?であれば、トランプ劇場よろしく大見得を切る会見をすればいいものを、小規模な侵攻なら容認と受け止められかねない発言をし、ウクライナ大統領に「侵攻に小規模も大規模もない」と叱られ、慌てて修正するとは何とも締まらない話です。ヒーローごっこはへっぴり腰でやるものではありません。
エネルギー競争の観点
実は、バイデン大統領とウクライナとは意外なつながりがあります。息子のハンター・バイデン氏がウクライナのエネルギー企業、ブリスマ社の役員を2014−19年にしていたのでした。この会社はウクライナのオリガルヒが創業し、親ロ政権下で天然資源相を務めた人物です。
元々、ウクライナは親ロ、親EUが半々、つまりどちらとも仲良くないと経済が成り立たず、ロシア民族も多く住んでいる状態で、選挙の度にどちらにつくかで悩む、いわゆるスウィング・ステートです。ということは、欧米側もロシア側もウクライナの大統領選のたびに選挙干渉工作をすることになります。(ロシアの選挙干渉は有名ですが、アメリカも負けず劣らずです。日本においても、冷戦時代ソ連が日本社会党に資金援助すれば、CIAは自民党へ資金を流しました。)
そして、このオリガルヒもロシアの選挙介入で政権をとった側についていたのですが、親EU側候補の告発で親ロ側の大統領は2014年2月ロシアへ亡命せざるを得ませんでした。親EU側政権は、オリガルヒが大臣時代に不正に国内の資源開発権を取得したのではないかという疑惑の目をブリスマ社に向けます。時あたかもオバマ政権が海外の汚職撲滅キャンペーンを展開していた時期にあたり、逆風をできるだけ緩和しようとハンター・バイデン氏やジョン・ケリー国務長官(当時)の家族に近い人物や元CIA職員を雇い、同社のイメージアップ作戦を展開し、何とかスキャンダルをもみ消すことに成功しました。
さて、同社が操業している場所に、問題のドネツク地方があります。実は、この地帯はシェールガスの埋蔵量が4兆立方トンと膨大にあると言われています。そして、ここにアメリカのシェブロン社と英蘭シェル社が食指を動かし、ウクライナ政府と開発契約を締結しました。
この背景には、ウクライナがロシアへの依存度を下げたいという意思があります。そしてもちろん、ロシアも同様にウクライナへの依存度を下げたいと考えています。ここで依存というのは、ソ連時代からある、ロシアからヨーロッパへの天然ガスパイプラインです。ロシアにとりドル箱の、このパイプラインはウクライナを経由している点が、ロシアにとりウクライナへの依存になりますが、一方ウクライナもロシアからパイプラインからの天然ガスを一部輸入しているので、ウクライナもロシアに依存している格好になります。
ソ連時代は実質同国内だったので問題なかったのですが、ソ連崩壊後二か国に分裂し、ウクライナにロシア依存以外の選択肢が生まれると、当然心は揺れ動きます。そして、両国が何かもめるとロシアがガス供給を止める挙に出るので、ウクライナはEUから天然ガスを逆輸入するようになり、さらには自国のシェールガス資源を欧米企業に開発させようと考えました。
一方、ロシアも負けてはいません。ロシアはウクライナを経由しない迂回パイプラインを建設します。これが、北海を通りドイツへ繋がるノルドストリームと東欧経由のサウスストリームプロジェクトです。このうち、サウスストリームがブルガリア等EUの同意を得られる見通しが立たないため、プーチン大統領は2014年12月サウスストリーム計画を正式に断念し、代わりにクリミア半島のすぐ脇のロシア領から黒海を北東から南西に横断する形でトルコへパイプラインを通すトルコストリームを計画しました。
恐らくその前からサウスストリームの命運を危ぶみ、黒海におけるトルコストリーム付近でのウクライナ政府の発言権を事前に奪うためでしょう、プーチン大統領は2014年3月にトルコストリームのロシア側の基地のすぐ近くのクリミア半島を併合しました。こうした迂回パイプラインの結果、ウクライナ通過量は1990年の85%から2018年には41%に低下しました。(ウクライナにとっては天然ガス通過料収入の減少につながります)
さらにウクライナには不幸が続きます。2014年夏頃原油価格が急降下し、ドバイ市場で1バレル約40ドルとなりました。そうなると、欧米企業にとりシェールガスは採算が合わないビジネスとなってしまい、相次ぎ撤退しました。また、ドネツク地方の地元民は、環境上の懸念からシェールガス開発に反対していました。これにロシアが武器等を秘かに渡し、ウクライナでの内乱に発展しています。(一方、ウクライナ政府には戦意喪失した欧米からの支援が乏しく、これまでウクライナ政府の支配権が及ばないエリアが生じたままであったと理解した方がいいでしょう。)
そして今、再び原油価格は当時の倍の80ドルにまで上昇しました。シェブロン社やシェル社のシェールガスへの意欲が再燃してもおかしくありません。となれば、欧米政府はドネツク地方を開発できる状態にしろというプレッシャーを受け、ロシアを悪者とし、ウクライナ政府への支援を増強し、ドネツク地方からロシアを撤退させようとしています。
一方ロシアとしても、本気でウクライナ産シェールガスをヨーロッパ市場へ売る事態となれば、地域独占状態の露ガスプロムとしては由々しき事態です。何せ、設備が老朽化し、非効率に生産しているロシア産のガスをヨーロッパへ高く売りつけ、自国にはウズベキスタン等中央アジア産の天然ガスを友誼価格で(現地の大統領以下政府高官を買収しているので)輸入している企業です。まともな価格競争をされたら、勝てないでしょう。
天然資源か武器しかまともな産業のないロシアとしては、ガスプロムの危機はそのままロシアの危機ですから、プーチン大統領としても引くに引けないでしょう。(もちろん、中国に全量売ることはできますが、それはそれで中国一国に依存することになるので、ロシアとしては避けたい選択です)
このように理解すると、欧米政府が強硬姿勢をとりつつ、期限を設けずに会話を継続している(会話を継続してこの厳冬をやり過ごし、暖房需要と共に原油価格の下落を待つ作戦)現状と辻褄が合うのではないでしょうか。早く春よ、来い。
参考文献(順不同)
Russia’s silent shale gas victory in Ukraine
(https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/russia-s-silent-shale-gas-victory-in-ukraine/)
Biden administration reportedly seeking conflict with Russia to 'restore credibility'
(https://thepostmillennial.com/biden-administration-seeking-conflict-with-russia-to-restore-credibility)
ロシア 天然ガスの野望 :3大パイプラインで目指す「グレートゲーム」の覇権
(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200225/se1/00m/020/055000c)
欧州ガスパイプラインの歴史的背景(その3)
(https://ieei.or.jp/2021/07/special201704027/)
Chevron pulls out of shale gas project in Ukraine
(https://www.ft.com/content/76b41d9c-847e-11e4-ba4f-00144feabdc0)
Shell walks away from Ukraine shale gas project
(https://www.rt.com/business/319944-shell-ukraine-gas-project/)
バイデン氏、ロシアのウクライナ「侵入」を予測 「小規模侵攻」なら対応議論も
(https://www.cnn.co.jp/usa/35182326.html)
トルコ・ストリームの開通式、イスタンブールで開催
(https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/d969b9eb080a20ce.html)
定期購読はこちらからご登録ください。
語られないものを視る眼 (mag2.com)
※当文章は著者の個人的見解であり、所属団体の意見を反映したものではありません。