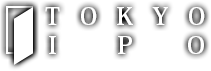東京IPO特別コラム:「歴史の重み:冷戦 その1 起源」
中国では歴史を評価するのに、50年を待たねばならないと言います。その50年には少し
欠けているのですが、旧ソ連側の資料が数多く公開され、学者たちの研究が大分進んでいま
すので、今冷戦を改めて振り返ってみたいと思います。
冷戦の基本構造
大まかにいえば、冷戦の基本構造は、資本主義と共産主義のイデオロギー対決に反植民地の
独立運動及び独立後の政治体制の模索がかけ合わさったといえばいいでしょうか。
日本では割合中立的に、アメリカ、西欧、日本を中心とする資本主義体制を西側陣営、ソ連
を中心とする共産主義体制を東側陣営と呼びましたが、両陣営は対立と和解のはざまを漂
っていました。その一方で、第二次世界大戦後宗主国である西欧諸国の力の衰えを背景に、
徐々に植民地が独立を果たし、新国家が数多く生まれた結果、両陣営のいずれかにつくかの
選択肢を迫られました。中には、第三の道を模索し、中立路線を追求した国もあり、イスラ
ム主義を選択した国もありました。
既に時系列で冷戦を描いた書物が数多くありますので、ここでは、ポイントをいくつかに絞
り振り返ってみたいと思います。
検証ポイント1:東西対立は必然であったか?
第二次世界大戦直後、英米もソ連も連合国という名の同じ同盟国でした。しかし、戦時中に
共通のナチス・ドイツと戦うための政略同盟ですから、勝利が見えてくる頃から元の相互不
信感が蘇ります。事実、スターリンには英米がソ連にナチス・ドイツと主に戦わせ、互いを
疲弊させるように画策しているのではないか?という不信感が常にありました。確かに、英
米軍がノルマンディー作戦を行う頃には、ソ連軍は、すでにドイツ国防軍の80%以上を屈
服させていましたから*、あながちスターリンの被害妄想の産物ではありません。
しかし、元々双方とも敵対関係になる気はありませんでした。けんかしないために、早くも
1944年10月には英ソ間で互いの影響圏(縄張り)を以下の通り決めたパーセンテージ
協定が結ばれました。**1815年のアフリカ分割と全く変わっていない思考です。(但し、
アメリカの反対にあい、潰えました)
・ルーマニア:ソ連90%、イギリス10%
・ギリシャ:ソ連10%、イギリス90%
・ユーゴ:ソ連50%、イギリス50%
・ハンガリー:ソ連50%(後に80%)、イギリス50%(後に20%)
・ブルガリア:ソ連75%(後に80%)、イギリス25%(後に20%)
一方、この協定からイギリスが、ソ連の第二次世界大戦での貢献を認め、東欧を譲歩したと
感じとることはできます。(事実、違い地中海や中東以東とイギリスとのエンパイア・ルー
ト確保を重視しました)そして、ここに臆病で日和見主義のスターリンは、ソ連の範囲を拡
張できる可能性をかぎ取ります。事実スターリンは、東地中海への進出を狙いトリポリタニ
ア(現リビアの首都周辺)を求め(英米の強硬な反対を前に撤回)、また戦中派兵していた
イランからの撤退を期日までに行わない等、英米の不信感を募らせる行動をとりました。こ
のようなスターリンを、封じ込め理論の提唱者として有名なジョージ・ケナンは、妥協は無
駄である、と看破しています。
スターリンは、あわよくばと狙った箇所は譲れても、ドイツ問題と東欧は別の話です。現在
のロシアの東欧観や安全保障観も垣間見えますので、ソ連の言い分を見てみましょう。「ソ
連の指導者たちは、将来の領土侵害から確実に本土を防衛しなければならないという強弱
観念を持つことになったのだ。地球の陸地面積の1/6を占め、アメリカの三倍の面積をも
つその地理的な広大さゆえ、適切な国防の確保はソ連にとって非常に深刻な問題であった。
経済的に最も重要な二つの地域、すなわち、ヨーロッパ・ロシアとシベリアは、ソ連の両端
に位置していた。そして、そのどちらもが国外からの攻撃にきわめて脆弱なことは、近年の
歴史が明らかにした通りだった。」*
すなわち、ドイツとソ連の間の東欧には強国がないので、ナポレオンやヒトラーのように、
その気になれば西欧諸国は、一気にモスクワやサンクトペテルブルクへ攻め込めるわけで
す。となれば、東欧はソ連が抑え、かつドイツは弱い国にしておかねばなりません。
そこでソ連は、「ポーランド及びその他の重要な東ヨーロッパ諸国に従順な親ソ政府を樹立
すること、ソ連の国境をロシア革命以前の国境線まで拡張する―つまり、バルト三国と戦前
のポーランドの東部を永久に併合する―こと」*を求めました。もしここでスターリンが妥
協していたら、その後の歴史は変わったかもしれません。
しかし、上記に加えてスターリンが求めたものは、「厳しい占領政策と組織的な非工業化、
過大な賠償金の支払い義務によってドイツから行動の自由を奪うことである。」*事実、ドイ
ツ内のソ連占領地域では、「ソ連軍によるすさまじい略奪が行われた。その間、200万人
ともいわれる女性がソ連兵に強姦された。さらに、賠償の一環として、解体された工場や線
路などのインフラがソ連に運び去られた。賠償金の取り立ても、1953年まで続いた。東
ドイツがソ連に支払った賠償額は、西ドイツがマーシャル・プランを通じて得られた援助額
に匹敵したともいわれている。加えて、何千人ものドイツ人の技術者、科学者、経営者、技
能保持者らがソ連に強制連行された。」***
一方、戦前からドイツはヨーロッパ経済の大きな部分を担っており、ヨーロッパ復興にはド
イツ経済再建は不可欠と、米英は見ていました。そのため、アメリカは14億ドルものヨー
ロッパ向け経済支援(マーシャル・プラン)に乗り出しました。
しかし、ソ連はこれを「アメリカとイギリスが、ヨーロッパ復興計画を通じて、西ドイツを
含む反ソ連の西側ブロックを形成しようとしていると確信した。それのみならず、マーシャ
ル・プランは、東ヨーロッパ経済に資本主義を浸透させ、ソ連の影響力を弱め、東欧諸国を
西側に引き付けよう」***としていると考え、東欧諸国には参加を断るよう強要しました。
このように方針が真っ向から衝突していれば、当初計画されていた占領4か国による協調
的なドイツ占領政策は不可能となり、ソ連がベルリン閉鎖を行い、英米がベルリン大空輸作
戦で対抗する事態に発展しました。結局、英米仏の占領区を西ドイツ、ソ連占領区を東ドイ
ツとして二分されるに至りました。加えて、アメリカ中心に北大西洋条約機構(NATO)と
いう軍事同盟が誕生しました。
ここに至っては、スターリンができることはほとんどなく、東欧諸国とワルシャワ条約機構
という軍事同盟を作り、ソ連版マーシャル・プラン(コメコン)に乗り出さざるを得ません。
「コメコンは、マーシャル・プランの模倣というより下手な風刺画にすぎなかった。スター
リン自身もその後、衛星国に対して対等とはいいがたい二国間関係を強制することで搾取
を行い、コメコンは信頼せず、なんら実体的な中身を整えなかった。結果的にこの二国間関
係によってソ連は、アメリカがマーシャル・プランを通して西側同盟国の復興のために供与
した14億ドルと同額相当の物資を、ソ連の復興のために衛星国から搾り取ることができ
た。ここに押し付けによるソ連帝国と「招かれた」帝国アメリカという大きな違いがあった。」
****
ソ連の戦後秩序計画立案者であるリトヴィノフは、「ソ連が明確な限度を定めることなしに
安全保障確保を追求したことが冷戦的対立の第一の原因であり、西側が早い段階で断固と
してこれに反対しなかったことが第二の原因である」****と言ったそうです。
但し、双方のリーダーに敵対する意思はなかったのに、互いの行動の意図をきちんとコミュ
ニケーションをとらずに、ボタンの掛け違いが続いた点も見逃せません。
アメリカも外交経験が乏しいトルーマン副大統領が、大統領に就任していました。当初トル
ーマン政権は、アメリカの経済力と原子爆弾の独占的保有が交渉上の切り札になると自信
を持ち、イギリスにも相談せずにソ連と直接交渉し、後で知ったイギリスを激怒させた場面
もありました。しかしやがてソ連への不信感を募らせると、1947年3月と早々に自由主
義体制と全体主義体制とに世界が二分されており、前者を保護すべきとするトルーマン・ド
クトリンを発表してしまいます。マーシャル・プラン発表の3か月も前の時点です。ドイツ
問題、原子力兵器の国際管理構想や、中東及び東地中海における利害等々、戦後経営で折り
合いを付けねばならない相手に向かって、あまりに直截な物言いは賢明とは思われません。
こうして、必ずしも必然ではなかった冷戦が始まり、その後も、こうしたボタンの掛け違い
は、続いていきます。
>>次号へ続く
*ロバート・マクマン著 「冷戦史」
**松岡完、広瀬佳一、竹中佳彦編著 「冷戦史」
***山本健著 「ヨーロッパ冷戦史」
****ヴォイチェフ・マストニー著 「冷戦とはなんだったのか」
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
欠けているのですが、旧ソ連側の資料が数多く公開され、学者たちの研究が大分進んでいま
すので、今冷戦を改めて振り返ってみたいと思います。
冷戦の基本構造
大まかにいえば、冷戦の基本構造は、資本主義と共産主義のイデオロギー対決に反植民地の
独立運動及び独立後の政治体制の模索がかけ合わさったといえばいいでしょうか。
日本では割合中立的に、アメリカ、西欧、日本を中心とする資本主義体制を西側陣営、ソ連
を中心とする共産主義体制を東側陣営と呼びましたが、両陣営は対立と和解のはざまを漂
っていました。その一方で、第二次世界大戦後宗主国である西欧諸国の力の衰えを背景に、
徐々に植民地が独立を果たし、新国家が数多く生まれた結果、両陣営のいずれかにつくかの
選択肢を迫られました。中には、第三の道を模索し、中立路線を追求した国もあり、イスラ
ム主義を選択した国もありました。
既に時系列で冷戦を描いた書物が数多くありますので、ここでは、ポイントをいくつかに絞
り振り返ってみたいと思います。
検証ポイント1:東西対立は必然であったか?
第二次世界大戦直後、英米もソ連も連合国という名の同じ同盟国でした。しかし、戦時中に
共通のナチス・ドイツと戦うための政略同盟ですから、勝利が見えてくる頃から元の相互不
信感が蘇ります。事実、スターリンには英米がソ連にナチス・ドイツと主に戦わせ、互いを
疲弊させるように画策しているのではないか?という不信感が常にありました。確かに、英
米軍がノルマンディー作戦を行う頃には、ソ連軍は、すでにドイツ国防軍の80%以上を屈
服させていましたから*、あながちスターリンの被害妄想の産物ではありません。
しかし、元々双方とも敵対関係になる気はありませんでした。けんかしないために、早くも
1944年10月には英ソ間で互いの影響圏(縄張り)を以下の通り決めたパーセンテージ
協定が結ばれました。**1815年のアフリカ分割と全く変わっていない思考です。(但し、
アメリカの反対にあい、潰えました)
・ルーマニア:ソ連90%、イギリス10%
・ギリシャ:ソ連10%、イギリス90%
・ユーゴ:ソ連50%、イギリス50%
・ハンガリー:ソ連50%(後に80%)、イギリス50%(後に20%)
・ブルガリア:ソ連75%(後に80%)、イギリス25%(後に20%)
一方、この協定からイギリスが、ソ連の第二次世界大戦での貢献を認め、東欧を譲歩したと
感じとることはできます。(事実、違い地中海や中東以東とイギリスとのエンパイア・ルー
ト確保を重視しました)そして、ここに臆病で日和見主義のスターリンは、ソ連の範囲を拡
張できる可能性をかぎ取ります。事実スターリンは、東地中海への進出を狙いトリポリタニ
ア(現リビアの首都周辺)を求め(英米の強硬な反対を前に撤回)、また戦中派兵していた
イランからの撤退を期日までに行わない等、英米の不信感を募らせる行動をとりました。こ
のようなスターリンを、封じ込め理論の提唱者として有名なジョージ・ケナンは、妥協は無
駄である、と看破しています。
スターリンは、あわよくばと狙った箇所は譲れても、ドイツ問題と東欧は別の話です。現在
のロシアの東欧観や安全保障観も垣間見えますので、ソ連の言い分を見てみましょう。「ソ
連の指導者たちは、将来の領土侵害から確実に本土を防衛しなければならないという強弱
観念を持つことになったのだ。地球の陸地面積の1/6を占め、アメリカの三倍の面積をも
つその地理的な広大さゆえ、適切な国防の確保はソ連にとって非常に深刻な問題であった。
経済的に最も重要な二つの地域、すなわち、ヨーロッパ・ロシアとシベリアは、ソ連の両端
に位置していた。そして、そのどちらもが国外からの攻撃にきわめて脆弱なことは、近年の
歴史が明らかにした通りだった。」*
すなわち、ドイツとソ連の間の東欧には強国がないので、ナポレオンやヒトラーのように、
その気になれば西欧諸国は、一気にモスクワやサンクトペテルブルクへ攻め込めるわけで
す。となれば、東欧はソ連が抑え、かつドイツは弱い国にしておかねばなりません。
そこでソ連は、「ポーランド及びその他の重要な東ヨーロッパ諸国に従順な親ソ政府を樹立
すること、ソ連の国境をロシア革命以前の国境線まで拡張する―つまり、バルト三国と戦前
のポーランドの東部を永久に併合する―こと」*を求めました。もしここでスターリンが妥
協していたら、その後の歴史は変わったかもしれません。
しかし、上記に加えてスターリンが求めたものは、「厳しい占領政策と組織的な非工業化、
過大な賠償金の支払い義務によってドイツから行動の自由を奪うことである。」*事実、ドイ
ツ内のソ連占領地域では、「ソ連軍によるすさまじい略奪が行われた。その間、200万人
ともいわれる女性がソ連兵に強姦された。さらに、賠償の一環として、解体された工場や線
路などのインフラがソ連に運び去られた。賠償金の取り立ても、1953年まで続いた。東
ドイツがソ連に支払った賠償額は、西ドイツがマーシャル・プランを通じて得られた援助額
に匹敵したともいわれている。加えて、何千人ものドイツ人の技術者、科学者、経営者、技
能保持者らがソ連に強制連行された。」***
一方、戦前からドイツはヨーロッパ経済の大きな部分を担っており、ヨーロッパ復興にはド
イツ経済再建は不可欠と、米英は見ていました。そのため、アメリカは14億ドルものヨー
ロッパ向け経済支援(マーシャル・プラン)に乗り出しました。
しかし、ソ連はこれを「アメリカとイギリスが、ヨーロッパ復興計画を通じて、西ドイツを
含む反ソ連の西側ブロックを形成しようとしていると確信した。それのみならず、マーシャ
ル・プランは、東ヨーロッパ経済に資本主義を浸透させ、ソ連の影響力を弱め、東欧諸国を
西側に引き付けよう」***としていると考え、東欧諸国には参加を断るよう強要しました。
このように方針が真っ向から衝突していれば、当初計画されていた占領4か国による協調
的なドイツ占領政策は不可能となり、ソ連がベルリン閉鎖を行い、英米がベルリン大空輸作
戦で対抗する事態に発展しました。結局、英米仏の占領区を西ドイツ、ソ連占領区を東ドイ
ツとして二分されるに至りました。加えて、アメリカ中心に北大西洋条約機構(NATO)と
いう軍事同盟が誕生しました。
ここに至っては、スターリンができることはほとんどなく、東欧諸国とワルシャワ条約機構
という軍事同盟を作り、ソ連版マーシャル・プラン(コメコン)に乗り出さざるを得ません。
「コメコンは、マーシャル・プランの模倣というより下手な風刺画にすぎなかった。スター
リン自身もその後、衛星国に対して対等とはいいがたい二国間関係を強制することで搾取
を行い、コメコンは信頼せず、なんら実体的な中身を整えなかった。結果的にこの二国間関
係によってソ連は、アメリカがマーシャル・プランを通して西側同盟国の復興のために供与
した14億ドルと同額相当の物資を、ソ連の復興のために衛星国から搾り取ることができ
た。ここに押し付けによるソ連帝国と「招かれた」帝国アメリカという大きな違いがあった。」
****
ソ連の戦後秩序計画立案者であるリトヴィノフは、「ソ連が明確な限度を定めることなしに
安全保障確保を追求したことが冷戦的対立の第一の原因であり、西側が早い段階で断固と
してこれに反対しなかったことが第二の原因である」****と言ったそうです。
但し、双方のリーダーに敵対する意思はなかったのに、互いの行動の意図をきちんとコミュ
ニケーションをとらずに、ボタンの掛け違いが続いた点も見逃せません。
アメリカも外交経験が乏しいトルーマン副大統領が、大統領に就任していました。当初トル
ーマン政権は、アメリカの経済力と原子爆弾の独占的保有が交渉上の切り札になると自信
を持ち、イギリスにも相談せずにソ連と直接交渉し、後で知ったイギリスを激怒させた場面
もありました。しかしやがてソ連への不信感を募らせると、1947年3月と早々に自由主
義体制と全体主義体制とに世界が二分されており、前者を保護すべきとするトルーマン・ド
クトリンを発表してしまいます。マーシャル・プラン発表の3か月も前の時点です。ドイツ
問題、原子力兵器の国際管理構想や、中東及び東地中海における利害等々、戦後経営で折り
合いを付けねばならない相手に向かって、あまりに直截な物言いは賢明とは思われません。
こうして、必ずしも必然ではなかった冷戦が始まり、その後も、こうしたボタンの掛け違い
は、続いていきます。
>>次号へ続く
*ロバート・マクマン著 「冷戦史」
**松岡完、広瀬佳一、竹中佳彦編著 「冷戦史」
***山本健著 「ヨーロッパ冷戦史」
****ヴォイチェフ・マストニー著 「冷戦とはなんだったのか」
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665