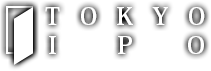東京IPO特別コラム:「歴史の重み:冷戦 その2 アメリカの論理」
検証ポイント2:冷戦中、東西陣営は正しく相手を理解していたのか?
なまじイデオロギーという、今まで国際政治が扱ったことがないものが入り込んでしまったため、互いの動きや意図の理解が大きく損なわれていました。結局軍事力というリアリズムが、大国間戦争を止めていたと理解した方がよさそうです。
アメリカの論理
封じ込め政策
冷戦当初、アメリカ軍幹部は、ソ連の軍事力を「対米戦争のリスクを冒すことができるほどソ連は強くないと判断して」*いました。むしろ英米の政治リーダーたちは、世界で共産主義への支持の高まりに乗じてソ連が利益を得るのではないかと懸念していました。その実、フランスやイタリアでは共産党への支持が高まっていましたし、ヨーロッパ諸国の植民地や中国では独立運動家の一部に共産主義への共鳴や共産党の動きがみられました。
少々長いですが、背景を説明しましょう。アメリカは、ヨーロッパ諸国と違い植民地を世界中に点在させておらず、一応宗主国イギリスから「独立」した旧「植民地」ですから、植民地支配に対し独立運動の発生は止められないであろうと心情的に独立運動家たちに味方し、フィリピンを独立させると戦中から約束していました。
一方イギリスでは、第二次世界大戦という国難を指導したチャーチル首相が、対ドイツ戦終結直後の1945年7月の総選挙で敗北しました。チャーチル首相は生粋の帝国主義者ですから、そのまま政権に就かせておけば、大英帝国の再建に若者たちを数多く世界中の植民地に送るに違いない、辺境の帝国を心配するより早く戦地に送った兵士たちを家に帰してほしい、というイギリス国民の強い意思表示と理解せざるを得ません。
言い換えれば、イギリス国民が大英帝国の継続に、ノーを突きつけたのです。これが意味するところは、イギリス軍を帝国の各地に充分に派遣できないということは、植民地での独立運動が暴力を伴う場合は抑えられないわけで、強硬な独立運動が発生すれば、「独立」を容認せざるを得ません。(但し、「独立」が具体的には何を意味するのかは後述します)
ここに、新たに大国となったアメリカと世界最大の植民地を有するイギリスが、基本方針として植民地支配を消極的であるにせよ、「独立」容認に方向転換したのですから、植民地解放はその後の潮流となっていきます。
しかし、いかに歴史の流れに逆らおうとも、アメリカの意思に逆らおうとも、意地汚くも植民地支配にしがみつき、本国の復興資金を捻出しようと考える、二流、三流ヨーロッパ宗主国がいます。こうした国々は、いつか起こるかもしれない独立運動への対策は、戦前からも暴力装置以外ありませんから、戦後直後から搾取する気満々でアジアやアフリカの植民地へ戻ってきます。当然のことながら、従来以上に搾取しようとするのですから、現地の抵抗にあうことは避けられません。
特に東南アジアでは日本軍が現地民による軍を組織していた経験を与え、日本政府と粘り強い交渉をし、形式的であろうと独立を果たした、あるいは独立を約束された国々ばかりですから、そう昔通りにはいきません。なるべくして暴力的な独立戦争に発展したのが、オランダ領インドネシアとフランス領ベトナムです。
この両国の独立運動リーダー、「ホー・チ・ミンとスカルノは、民族自決を支持するという、第二次世界大戦中にアメリカが行った宣言を根拠としてアメリカに支援を訴えた。しかしアメリカがその訴えを無視したことに、二人は大きく失望した。」*そこで、ホー・チ・ミンは共産党という選択肢を追求した結果、フランスやアメリカを敵に回して、独立を勝ち取りました。スカルノはインドネシア内の共産党の蜂起を鎮圧することで自らを西側陣営であることを証明したことにより、アメリカがオランダに独立を認めるよう圧力をかけ、独立を獲得したのでした。
この2か国の例が示す通り、宗主国やアメリカがうまく立ち回らないと、新規独立国は東西陣営のどちらに転んでもおかしくありません。そこで世界中に共産主義という病が「蔓延」しないように、東側陣営の患者(国)以上に拡散させない、「封じ込め」政策がトルーマン政権から提唱されるようになります。この政策により、共産主義に染まりそうな国への介入をするようになります。当初はギリシャやトルコ等ヨーロッパを中心に考えていましたが、なし崩し的に地理的な区切りがなくなり、対象は世界中になりました。
ちなみに、この「封じ込め」という概念は、元々伝染病対策の用語です。伝染病が非常に危険であるが有効な治療法や免疫手段がない場合に使われます。よって、この考え方自体は、積極的に共産主義を攻撃する方針ではなく、特にソ連の自壊を待つという戦略でもありません。ましてや、日本や西欧以外に多額の経済援助を行い、共産主義に染まらないように資本主義社会へ導くような、積極的な「予防」措置をとることを意味するものではありません。言い換えれば、世界を囲碁盤のように見立て、ソ連の指してきたエリアならどこででも、勝負(代理戦争)しようとしていました。
もちろん、まったく善意からの経済援助がなかったわけではありません。また、多くのアフリカが独立した時期に、ソ連に非難されないよう、また西側陣営への幻滅を抱かないよう、アメリカ国内の黒人の地位向上を提唱した1950−60年代の公民権運動が、ワシントンの支持を得ました。
しかし、援助国の選定には多分に政治的な手心が加わっていましたし、独裁政権でも西側陣営を表明していれば、人権問題には目をつぶり、援助しました。特に中南米はアメリカの「裏庭」的概念が消えず、反米を唱える政権には容赦なく、CIAによる政権転覆作戦を展開しました。このようなアメリカの言動不一致の矛盾を目の当たりにしたチェ・ゲバラやカストロらが、共産主義に活路を見出そうとし、キューバ革命が成功しました。このように封じ込め政策は、一貫性があったものではありませんでした。
加えて、アメリカの、敵か味方か態度を鮮明にさせることを強要し、中立を許さない二元論的思考が、民族主義の傾向の強い第三世界リーダー達を疎遠にしました。例えば、イランのモサデク首相は、国内で操業しているイギリス系石油会社(アングロ・イラニアン石油)がイランへその利潤をほとんど還元しないため、石油国有化(アングロ・イラニアン石油資産の凍結)を宣言し、イギリスの猛反発にあったため、これに対抗するためにソ連に接近しました。結局CIAがモサデク政権転覆作戦を展開し、パーレビ皇帝の親政という形でイランを親米英政権に「矯正」ました。
また、エジプトのナセル大統領は、中華人民共和国を承認する等アメリカをいらだたせる政策を採ったため、エジプトにとり大規模プロジェクト、アスワン・ハイ・ダム建設への資金援助を、アメリカが停止しました。報復措置としてナセル大統領はスエズ運河を国有化し、これに反発したスエズ運河の所有者である英仏が軍事介入しました。当然ソ連がこれを非難し、道義的に劣勢に立たされたアメリカは英仏に撤退を要求し、事態を収拾せざるを得ませんでした。(その後、アスワン・ハイ・ダムは、ソ連の支援で建設されました。)
ベトナム戦争がもたらした軍縮交渉
しかし、世界中に介入を辞さないアメリカの姿勢は、ベトナム戦争による不毛な体力消耗により、見直しを迫られます。それが可能にしたのは、リアリストのニクソン大統領とキッシンジャー国務長官のコンビです。
当時のアメリカでは異様だったでしょうが、イデオロギーを取り払ってソ連を見れば、純粋にその軍事力だけが懸念事項でした。ですから、ソ連と軍縮交渉をし、イデオロギー対決(できるだけ介入しない)をしなければ、アメリカの資源の浪費を抑えられます。恐らく、この時が、アメリカがソ連を一番理解し、真っ当に対応したタイミングだったでしょうか。そのつもりで、ニクソン大統領はソ連と戦略兵器制限交渉(SALT I)と交渉し、米ソ間のデタント(雪解け)時代が続きました。
それでも超大国の介入は続く
しかし、この1970年代という時代は、第三世界では独立運動リーダーの第一世代が第二世代へと世代交代した時期にあたりました。そこで、独立運動や革命はうまくいったものの、この頃原材料の国際価格が下落し、往々にしてその輸出に頼っている第三世界の国々でなかなか人々の生活が向上しないこともあり、第二世代は第一世代の選択を否定し、共産主義へ傾倒する傾向が見られました。***そこで、ソ連はアンゴラ、南イエメン、エチオピア、80年代にはアフガニスタンに軍事援助を始めます。
これがアメリカでは大問題になり、デタントは弱腰だとして、強硬な反共主義者のレーガン政権が誕生したとたん、ソ連を「悪の帝国」と呼び、自信満々に戦略防衛構想(SDI、通称スターウォーズ計画)をぶち上げるのですから、デタントムードは一気に吹き飛びました。しかし、グラスノスチやペレストロイカを掲げたゴルバチョフ書記長の登場で、レーガン政権は今までと異なり、話せる相手と認識を改めるようになり、やがて冷戦終結に繋がりました。
>>次号へ続く
*ロバート・マクマン著 「冷戦史」
**ヴォイチェフ・マストニー著 「冷戦とはなんだったのか」
*** O.A.ウェスタッド著 「グローバル冷戦史」
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
なまじイデオロギーという、今まで国際政治が扱ったことがないものが入り込んでしまったため、互いの動きや意図の理解が大きく損なわれていました。結局軍事力というリアリズムが、大国間戦争を止めていたと理解した方がよさそうです。
アメリカの論理
封じ込め政策
冷戦当初、アメリカ軍幹部は、ソ連の軍事力を「対米戦争のリスクを冒すことができるほどソ連は強くないと判断して」*いました。むしろ英米の政治リーダーたちは、世界で共産主義への支持の高まりに乗じてソ連が利益を得るのではないかと懸念していました。その実、フランスやイタリアでは共産党への支持が高まっていましたし、ヨーロッパ諸国の植民地や中国では独立運動家の一部に共産主義への共鳴や共産党の動きがみられました。
少々長いですが、背景を説明しましょう。アメリカは、ヨーロッパ諸国と違い植民地を世界中に点在させておらず、一応宗主国イギリスから「独立」した旧「植民地」ですから、植民地支配に対し独立運動の発生は止められないであろうと心情的に独立運動家たちに味方し、フィリピンを独立させると戦中から約束していました。
一方イギリスでは、第二次世界大戦という国難を指導したチャーチル首相が、対ドイツ戦終結直後の1945年7月の総選挙で敗北しました。チャーチル首相は生粋の帝国主義者ですから、そのまま政権に就かせておけば、大英帝国の再建に若者たちを数多く世界中の植民地に送るに違いない、辺境の帝国を心配するより早く戦地に送った兵士たちを家に帰してほしい、というイギリス国民の強い意思表示と理解せざるを得ません。
言い換えれば、イギリス国民が大英帝国の継続に、ノーを突きつけたのです。これが意味するところは、イギリス軍を帝国の各地に充分に派遣できないということは、植民地での独立運動が暴力を伴う場合は抑えられないわけで、強硬な独立運動が発生すれば、「独立」を容認せざるを得ません。(但し、「独立」が具体的には何を意味するのかは後述します)
ここに、新たに大国となったアメリカと世界最大の植民地を有するイギリスが、基本方針として植民地支配を消極的であるにせよ、「独立」容認に方向転換したのですから、植民地解放はその後の潮流となっていきます。
しかし、いかに歴史の流れに逆らおうとも、アメリカの意思に逆らおうとも、意地汚くも植民地支配にしがみつき、本国の復興資金を捻出しようと考える、二流、三流ヨーロッパ宗主国がいます。こうした国々は、いつか起こるかもしれない独立運動への対策は、戦前からも暴力装置以外ありませんから、戦後直後から搾取する気満々でアジアやアフリカの植民地へ戻ってきます。当然のことながら、従来以上に搾取しようとするのですから、現地の抵抗にあうことは避けられません。
特に東南アジアでは日本軍が現地民による軍を組織していた経験を与え、日本政府と粘り強い交渉をし、形式的であろうと独立を果たした、あるいは独立を約束された国々ばかりですから、そう昔通りにはいきません。なるべくして暴力的な独立戦争に発展したのが、オランダ領インドネシアとフランス領ベトナムです。
この両国の独立運動リーダー、「ホー・チ・ミンとスカルノは、民族自決を支持するという、第二次世界大戦中にアメリカが行った宣言を根拠としてアメリカに支援を訴えた。しかしアメリカがその訴えを無視したことに、二人は大きく失望した。」*そこで、ホー・チ・ミンは共産党という選択肢を追求した結果、フランスやアメリカを敵に回して、独立を勝ち取りました。スカルノはインドネシア内の共産党の蜂起を鎮圧することで自らを西側陣営であることを証明したことにより、アメリカがオランダに独立を認めるよう圧力をかけ、独立を獲得したのでした。
この2か国の例が示す通り、宗主国やアメリカがうまく立ち回らないと、新規独立国は東西陣営のどちらに転んでもおかしくありません。そこで世界中に共産主義という病が「蔓延」しないように、東側陣営の患者(国)以上に拡散させない、「封じ込め」政策がトルーマン政権から提唱されるようになります。この政策により、共産主義に染まりそうな国への介入をするようになります。当初はギリシャやトルコ等ヨーロッパを中心に考えていましたが、なし崩し的に地理的な区切りがなくなり、対象は世界中になりました。
ちなみに、この「封じ込め」という概念は、元々伝染病対策の用語です。伝染病が非常に危険であるが有効な治療法や免疫手段がない場合に使われます。よって、この考え方自体は、積極的に共産主義を攻撃する方針ではなく、特にソ連の自壊を待つという戦略でもありません。ましてや、日本や西欧以外に多額の経済援助を行い、共産主義に染まらないように資本主義社会へ導くような、積極的な「予防」措置をとることを意味するものではありません。言い換えれば、世界を囲碁盤のように見立て、ソ連の指してきたエリアならどこででも、勝負(代理戦争)しようとしていました。
もちろん、まったく善意からの経済援助がなかったわけではありません。また、多くのアフリカが独立した時期に、ソ連に非難されないよう、また西側陣営への幻滅を抱かないよう、アメリカ国内の黒人の地位向上を提唱した1950−60年代の公民権運動が、ワシントンの支持を得ました。
しかし、援助国の選定には多分に政治的な手心が加わっていましたし、独裁政権でも西側陣営を表明していれば、人権問題には目をつぶり、援助しました。特に中南米はアメリカの「裏庭」的概念が消えず、反米を唱える政権には容赦なく、CIAによる政権転覆作戦を展開しました。このようなアメリカの言動不一致の矛盾を目の当たりにしたチェ・ゲバラやカストロらが、共産主義に活路を見出そうとし、キューバ革命が成功しました。このように封じ込め政策は、一貫性があったものではありませんでした。
加えて、アメリカの、敵か味方か態度を鮮明にさせることを強要し、中立を許さない二元論的思考が、民族主義の傾向の強い第三世界リーダー達を疎遠にしました。例えば、イランのモサデク首相は、国内で操業しているイギリス系石油会社(アングロ・イラニアン石油)がイランへその利潤をほとんど還元しないため、石油国有化(アングロ・イラニアン石油資産の凍結)を宣言し、イギリスの猛反発にあったため、これに対抗するためにソ連に接近しました。結局CIAがモサデク政権転覆作戦を展開し、パーレビ皇帝の親政という形でイランを親米英政権に「矯正」ました。
また、エジプトのナセル大統領は、中華人民共和国を承認する等アメリカをいらだたせる政策を採ったため、エジプトにとり大規模プロジェクト、アスワン・ハイ・ダム建設への資金援助を、アメリカが停止しました。報復措置としてナセル大統領はスエズ運河を国有化し、これに反発したスエズ運河の所有者である英仏が軍事介入しました。当然ソ連がこれを非難し、道義的に劣勢に立たされたアメリカは英仏に撤退を要求し、事態を収拾せざるを得ませんでした。(その後、アスワン・ハイ・ダムは、ソ連の支援で建設されました。)
ベトナム戦争がもたらした軍縮交渉
しかし、世界中に介入を辞さないアメリカの姿勢は、ベトナム戦争による不毛な体力消耗により、見直しを迫られます。それが可能にしたのは、リアリストのニクソン大統領とキッシンジャー国務長官のコンビです。
当時のアメリカでは異様だったでしょうが、イデオロギーを取り払ってソ連を見れば、純粋にその軍事力だけが懸念事項でした。ですから、ソ連と軍縮交渉をし、イデオロギー対決(できるだけ介入しない)をしなければ、アメリカの資源の浪費を抑えられます。恐らく、この時が、アメリカがソ連を一番理解し、真っ当に対応したタイミングだったでしょうか。そのつもりで、ニクソン大統領はソ連と戦略兵器制限交渉(SALT I)と交渉し、米ソ間のデタント(雪解け)時代が続きました。
それでも超大国の介入は続く
しかし、この1970年代という時代は、第三世界では独立運動リーダーの第一世代が第二世代へと世代交代した時期にあたりました。そこで、独立運動や革命はうまくいったものの、この頃原材料の国際価格が下落し、往々にしてその輸出に頼っている第三世界の国々でなかなか人々の生活が向上しないこともあり、第二世代は第一世代の選択を否定し、共産主義へ傾倒する傾向が見られました。***そこで、ソ連はアンゴラ、南イエメン、エチオピア、80年代にはアフガニスタンに軍事援助を始めます。
これがアメリカでは大問題になり、デタントは弱腰だとして、強硬な反共主義者のレーガン政権が誕生したとたん、ソ連を「悪の帝国」と呼び、自信満々に戦略防衛構想(SDI、通称スターウォーズ計画)をぶち上げるのですから、デタントムードは一気に吹き飛びました。しかし、グラスノスチやペレストロイカを掲げたゴルバチョフ書記長の登場で、レーガン政権は今までと異なり、話せる相手と認識を改めるようになり、やがて冷戦終結に繋がりました。
>>次号へ続く
*ロバート・マクマン著 「冷戦史」
**ヴォイチェフ・マストニー著 「冷戦とはなんだったのか」
*** O.A.ウェスタッド著 「グローバル冷戦史」
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665