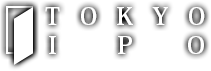東京IPO特別コラム:「人命は「空飛ぶ宮殿」よりも軽い?」
今年10月イスラエルとハマスの間で休戦協定が成立し、ハマスからはイスラエル人の人質が解放され、イスラエルからはパレスチナ人の拘留者が解放されました。また部分的にイスラエル軍がガザ地区から撤退し、長らく待たれた人道支援が細々と入るようになりました。
一見めでたいことですが、ここでは3つの「なぜ」を投げかけ、考えてみたいと思います。
「なぜ」今なのか?
イスラエル人人質は2023年10月から拉致されていますが、イスラエル・ハマス間で停戦協定が生まれそうなタイミングは、何度かありました。しかし、その都度イスラエルが潰してきました。そのため、多くの人々は疑いの眼を向けていたわけですが、なぜ今回は成立したのでしょう?
きっかけは、イスラエルによるカタール空爆です。これにより、ますますアメリカは地域安全を保障してくれる国ではないという認識を、中東の人々は強め、サウジアラビアはパキスタンと軍事協定まで締結しました。
通常こうした政治的にセンシティブな事柄については、ネタニヤフ首相はツーカーの仲であるトランプ大統領に個人的に伝えるべき内容ですが、今回敢えて行っていません。但し、アメリカ・イスラエル軍間のコミュニケーションはあったようで、トランプ大統領は米軍高官から報告を受けたと言います。そして、トランプ大統領は、不満を隠さなかったと報じられています。*
その後、アメリカ・ファーストを掲げるトランプ大統領にしては珍しいことですが、10月カタールへの攻撃はアメリカへの攻撃とみなすという、異例の大統領令を出した上、ネタニヤフ首相からカタール首相へ、同空爆が民間人を巻き添えで死亡させたことに対し、謝罪がありました。(同盟国という面では格上のヨーロッパ諸国には、あんなに辛く当たるのに。。。)
ちなみに、大統領令は法律と異なり、署名した大統領の任期中に限り有効な指示書です。次期大統領が署名しなければ、その時点で失効します。他国との条約締結や戦争宣言には、米議会の承認を必要としますが、急を要する、または議会の承認を得られそうにない案件には、歴代大統領はこの手を使います。
さて、この大統領令は、イスラエルは二度とカタール国土を攻撃しないという約束ですが、これを実現させるには、イスラエルのコミットメントと、その攻撃口実を潰さなければ、米軍派兵が要求されかねません。そして、それはトランプ大統領が最も避けたい事態です。では、イスラエルの攻撃口実とは何かといえば、パレスチナ問題への解決への道筋をつけることに外なりません。しかし、何度も行われては破綻した経緯があります。
失敗の本質は、イスラエル政府がパレスチナと共存する意思を持たないからですが、時々アメリカからの強い圧力を受け、パレスチナ側が反対するような条件を付けた「計画」を練り、パレスチナ側に断らせる、あるいは一時的に受け入れても、破綻するように仕組まれているわけです。それでも、アメリカは往々にして、和平を「演出」し、世界に楽観ムードを誇大宣伝することで満足します。
そして、再び過去の失敗を繰り返すべく、トランプ大統領は10日間程度で「20か条の平和計画」なるものを作成し、まずは一番簡単な人質交換が実現されました。
なぜトランプ大統領はアメリカ・ファーストを貫かなかったのか?
過去カタール王室から、「空飛ぶ宮殿」を賄賂にもらったからでしょうか?トランプ不動産がカタールにゴルフリゾートを計画しているからでしょうか?政治家である前にビジネスマンであるトランプ大統領の場合、このCNN説**は、確かに否定し難いのですが。。。(類似の俗物的な側面から、ノーベル平和賞がほしいから、という理由を挙げることもできます)
一応、まともな理由も、いくつか考えられます。今後対中政策を考える上で、アメリカの同盟国の協力が必要であり、あまりにアメリカが頼りない同盟国というイメージは、早期に打ち消さないと、必要な時に充分に同盟国の協力を得られないリスクが、あります。
また、その後トランプ大統領が中東にもたらしたいイスラエルとアラブ諸国、最終的にはサウジアラビアとの国交樹立の実現には、カタールの怒りは至極当然すぎる障害物であり、素早く対応することで、カタールや近隣アラブ諸国の怒りを鎮めようとしたとも考えられます。
あるいは、対ロ政策、または来年の中間選挙に向け、これ以上の原油価格高騰に向けて動かないように、協力を得たかったかもしれません。ロシアは中東産油国の協力があればこそ、原油価格が高止まりとなり、エネルギー資源を売るしかないロシアの、ウクライナ戦争継続に大きく貢献しているわけです。よって、中東産油国がこぞって減産しないというメッセージは、アメリカ主導の経済制裁(これ以上強化しても実質的な効果がないレベルまで来ています)よりも、ロシアにとり大きなダメージとなります。そして、原油高騰が起きないことは、来年の中間選挙にもプラスに働きます。
しかし、これらトランプ大統領の思惑は、前々からあるわけで、必要条件であっても、充分条件ではありません。
そこで、別の角度から検討してみましょう。
なぜネタニヤフ首相は和平に応じたのか?
ネタニヤフ首相は、上記に挙げたようなトランプ大統領の都合で、停戦に応じるものでしょうか?今までの経緯からして、納得感はありません。ただでさえ、自国民の人質の人命優先を求める声に応じず、ひたすら自らの政権維持(諸々の汚職スキャンダル訴訟を延期)のため、「戦争」を利用してきた人物です。トランプ大統領やその中東特使、ウィットコフ氏が、イスラエル国内でネタニヤフ首相を持ち上げても、イスラエルの聴衆がブーイングや不賛同の意思を示した事でも、明らかでしょう。
このような人物が、和平に応じるとすれば、汚職スキャンダル訴訟に勝てる自信を得られたか、もっと大きな悪企みの一環か、のいずれかしかないでしょう。前者は、国際社会の非難を無視して2年も戦争を継続していたわけですから、その可能性はまずないわけで、もっと大きな悪企みがあるのではないかと、危惧しています。
では、もっと大きな悪企みとは何があり得るでしょう?
ヒントは、「20か条の平和計画」にあります。この計画はパレスチナ人にとって、過酷です。まず、自治政府を立ち上げるといっても、主な団体−パレスチナ解放機構(PLO)、ハマス、ファタハ等−は、政治主体として政権入りを許されていません。いったんこれらの組織を解体したことにして、名称を変えて新政党を作ろうとしても、主だったリーダーの大半は、既に死亡しているか、イスラエルの獄中でしょう。(当然、こういう人々は解放されません)
そういう状況下で、本当に選挙できますか?パレスチナ人同士で、誰をリーダーとするかで、色々議論が必要であることは確かです。
次に、「第二段階」とされるハマスの武装解除ですが、どこまで実現可能でしょうか?一応、武器をイスラエル軍に差し出した者には恩赦を与えパレスチナに残れます。あるいは国外に流浪に出るという選択もあり、その場合は、二度と祖国に戻れないと言います。
しかし、何度も約束を違え、人権侵害も甚だしい虐殺や拷問を平気で行う、イスラエル政府を、誰が信じるというのでしょう?部分的には武器の明け渡しには応じられても、完全には無理でしょう。素直に武器を明け渡し、その場で射殺されない保証はどこにもないのです。既に、イスラエル人の人質を全員解放し、武器まで明け渡しては、イスラエル軍の横暴に対抗する術は、もはやありません。実際、イスラエル軍が無辜のパレスチナ人を殺害し、人道支援の流入も制限しているという報道がなされています。
一方、全く応じないとなれば、ハマスが第二段階の約束に違反したとして、イスラエル軍とアメリカは再び、戦争状態に戻ります。そうしたジレンマを分かった上で、ハマスやパレスチナ人の一般市民は、常にイスラエル軍に爆撃されず、夜防弾チョッキを着ずに安眠し、朝目覚める日々を選択したわけです。
こうした状況下、ハマスが武器を隠し持っていることが判明する、あるいは第三のインティファーダが発生し、無辜の民が投石等で戦い始めるのは、正直時間の問題です。ある程度ハマスは武器を明け渡すでしょうから、その接触の過程でイスラエル軍が知らないハマス拠点も明らかになるでしょう。何せ、2年も経て生存しているイスラエル人人質20名の行方は、とうとう最後まで分からなかったのですから、まだ相当数あるのでしょう。
そして、その頃までには散り散りになっていたパレスチナ市民は、また都市に集まるでしょう。これは、攻撃対象が集まっている状態ともいえます。バラバラに潜んでいるパレスチナ市民の隠れ家を一つ一つ見つけ出し、攻撃するより、はるかに効率よく殺害できます。しかも、その頃までにはハマスが武器をある程度明け渡し終わっているでしょうから、抵抗力は従来よりも小規模になるでしょう。そうやって、あわよくば全滅させたい、そんな計画を練り、心にもない和平に合意したのではないか、とも考えられます。
そうなることが見えているから、ネタニヤフ首相は、トランプ大統領の顔を立て、和平に応じたのでしょう。汚職スキャンダル訴訟にしても、そうすぐに投獄されることはありません。裁判中に戦争再開になれば、再び戦時内閣として裁判を中断し、政権続投すればいいわけです。
このように考えれば、全て辻褄が合うのですが、和平が続くことを祈るばかりです。
* “Once Again, Israel Leaves Trump in the Dark as It Conducts a Military Attack”, New York Times, September 9, 2025.
https://www.nytimes.com/2025/09/09/us/politics/israel-trump-gaza-qatar-bombing.html
** “Why Trump’s pledge to defend Qatar is so extraordinary”, CNN, October 1, 2025.
https://edition.cnn.com/2025/10/01/politics/qatar-pledge-trump-analysis
吉川 由紀枝 ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
著書:「現代国際政治の全体像が分かる!〜世界史でゲームのルールを探る〜」
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
一見めでたいことですが、ここでは3つの「なぜ」を投げかけ、考えてみたいと思います。
「なぜ」今なのか?
イスラエル人人質は2023年10月から拉致されていますが、イスラエル・ハマス間で停戦協定が生まれそうなタイミングは、何度かありました。しかし、その都度イスラエルが潰してきました。そのため、多くの人々は疑いの眼を向けていたわけですが、なぜ今回は成立したのでしょう?
きっかけは、イスラエルによるカタール空爆です。これにより、ますますアメリカは地域安全を保障してくれる国ではないという認識を、中東の人々は強め、サウジアラビアはパキスタンと軍事協定まで締結しました。
通常こうした政治的にセンシティブな事柄については、ネタニヤフ首相はツーカーの仲であるトランプ大統領に個人的に伝えるべき内容ですが、今回敢えて行っていません。但し、アメリカ・イスラエル軍間のコミュニケーションはあったようで、トランプ大統領は米軍高官から報告を受けたと言います。そして、トランプ大統領は、不満を隠さなかったと報じられています。*
その後、アメリカ・ファーストを掲げるトランプ大統領にしては珍しいことですが、10月カタールへの攻撃はアメリカへの攻撃とみなすという、異例の大統領令を出した上、ネタニヤフ首相からカタール首相へ、同空爆が民間人を巻き添えで死亡させたことに対し、謝罪がありました。(同盟国という面では格上のヨーロッパ諸国には、あんなに辛く当たるのに。。。)
ちなみに、大統領令は法律と異なり、署名した大統領の任期中に限り有効な指示書です。次期大統領が署名しなければ、その時点で失効します。他国との条約締結や戦争宣言には、米議会の承認を必要としますが、急を要する、または議会の承認を得られそうにない案件には、歴代大統領はこの手を使います。
さて、この大統領令は、イスラエルは二度とカタール国土を攻撃しないという約束ですが、これを実現させるには、イスラエルのコミットメントと、その攻撃口実を潰さなければ、米軍派兵が要求されかねません。そして、それはトランプ大統領が最も避けたい事態です。では、イスラエルの攻撃口実とは何かといえば、パレスチナ問題への解決への道筋をつけることに外なりません。しかし、何度も行われては破綻した経緯があります。
失敗の本質は、イスラエル政府がパレスチナと共存する意思を持たないからですが、時々アメリカからの強い圧力を受け、パレスチナ側が反対するような条件を付けた「計画」を練り、パレスチナ側に断らせる、あるいは一時的に受け入れても、破綻するように仕組まれているわけです。それでも、アメリカは往々にして、和平を「演出」し、世界に楽観ムードを誇大宣伝することで満足します。
そして、再び過去の失敗を繰り返すべく、トランプ大統領は10日間程度で「20か条の平和計画」なるものを作成し、まずは一番簡単な人質交換が実現されました。
なぜトランプ大統領はアメリカ・ファーストを貫かなかったのか?
過去カタール王室から、「空飛ぶ宮殿」を賄賂にもらったからでしょうか?トランプ不動産がカタールにゴルフリゾートを計画しているからでしょうか?政治家である前にビジネスマンであるトランプ大統領の場合、このCNN説**は、確かに否定し難いのですが。。。(類似の俗物的な側面から、ノーベル平和賞がほしいから、という理由を挙げることもできます)
一応、まともな理由も、いくつか考えられます。今後対中政策を考える上で、アメリカの同盟国の協力が必要であり、あまりにアメリカが頼りない同盟国というイメージは、早期に打ち消さないと、必要な時に充分に同盟国の協力を得られないリスクが、あります。
また、その後トランプ大統領が中東にもたらしたいイスラエルとアラブ諸国、最終的にはサウジアラビアとの国交樹立の実現には、カタールの怒りは至極当然すぎる障害物であり、素早く対応することで、カタールや近隣アラブ諸国の怒りを鎮めようとしたとも考えられます。
あるいは、対ロ政策、または来年の中間選挙に向け、これ以上の原油価格高騰に向けて動かないように、協力を得たかったかもしれません。ロシアは中東産油国の協力があればこそ、原油価格が高止まりとなり、エネルギー資源を売るしかないロシアの、ウクライナ戦争継続に大きく貢献しているわけです。よって、中東産油国がこぞって減産しないというメッセージは、アメリカ主導の経済制裁(これ以上強化しても実質的な効果がないレベルまで来ています)よりも、ロシアにとり大きなダメージとなります。そして、原油高騰が起きないことは、来年の中間選挙にもプラスに働きます。
しかし、これらトランプ大統領の思惑は、前々からあるわけで、必要条件であっても、充分条件ではありません。
そこで、別の角度から検討してみましょう。
なぜネタニヤフ首相は和平に応じたのか?
ネタニヤフ首相は、上記に挙げたようなトランプ大統領の都合で、停戦に応じるものでしょうか?今までの経緯からして、納得感はありません。ただでさえ、自国民の人質の人命優先を求める声に応じず、ひたすら自らの政権維持(諸々の汚職スキャンダル訴訟を延期)のため、「戦争」を利用してきた人物です。トランプ大統領やその中東特使、ウィットコフ氏が、イスラエル国内でネタニヤフ首相を持ち上げても、イスラエルの聴衆がブーイングや不賛同の意思を示した事でも、明らかでしょう。
このような人物が、和平に応じるとすれば、汚職スキャンダル訴訟に勝てる自信を得られたか、もっと大きな悪企みの一環か、のいずれかしかないでしょう。前者は、国際社会の非難を無視して2年も戦争を継続していたわけですから、その可能性はまずないわけで、もっと大きな悪企みがあるのではないかと、危惧しています。
では、もっと大きな悪企みとは何があり得るでしょう?
ヒントは、「20か条の平和計画」にあります。この計画はパレスチナ人にとって、過酷です。まず、自治政府を立ち上げるといっても、主な団体−パレスチナ解放機構(PLO)、ハマス、ファタハ等−は、政治主体として政権入りを許されていません。いったんこれらの組織を解体したことにして、名称を変えて新政党を作ろうとしても、主だったリーダーの大半は、既に死亡しているか、イスラエルの獄中でしょう。(当然、こういう人々は解放されません)
そういう状況下で、本当に選挙できますか?パレスチナ人同士で、誰をリーダーとするかで、色々議論が必要であることは確かです。
次に、「第二段階」とされるハマスの武装解除ですが、どこまで実現可能でしょうか?一応、武器をイスラエル軍に差し出した者には恩赦を与えパレスチナに残れます。あるいは国外に流浪に出るという選択もあり、その場合は、二度と祖国に戻れないと言います。
しかし、何度も約束を違え、人権侵害も甚だしい虐殺や拷問を平気で行う、イスラエル政府を、誰が信じるというのでしょう?部分的には武器の明け渡しには応じられても、完全には無理でしょう。素直に武器を明け渡し、その場で射殺されない保証はどこにもないのです。既に、イスラエル人の人質を全員解放し、武器まで明け渡しては、イスラエル軍の横暴に対抗する術は、もはやありません。実際、イスラエル軍が無辜のパレスチナ人を殺害し、人道支援の流入も制限しているという報道がなされています。
一方、全く応じないとなれば、ハマスが第二段階の約束に違反したとして、イスラエル軍とアメリカは再び、戦争状態に戻ります。そうしたジレンマを分かった上で、ハマスやパレスチナ人の一般市民は、常にイスラエル軍に爆撃されず、夜防弾チョッキを着ずに安眠し、朝目覚める日々を選択したわけです。
こうした状況下、ハマスが武器を隠し持っていることが判明する、あるいは第三のインティファーダが発生し、無辜の民が投石等で戦い始めるのは、正直時間の問題です。ある程度ハマスは武器を明け渡すでしょうから、その接触の過程でイスラエル軍が知らないハマス拠点も明らかになるでしょう。何せ、2年も経て生存しているイスラエル人人質20名の行方は、とうとう最後まで分からなかったのですから、まだ相当数あるのでしょう。
そして、その頃までには散り散りになっていたパレスチナ市民は、また都市に集まるでしょう。これは、攻撃対象が集まっている状態ともいえます。バラバラに潜んでいるパレスチナ市民の隠れ家を一つ一つ見つけ出し、攻撃するより、はるかに効率よく殺害できます。しかも、その頃までにはハマスが武器をある程度明け渡し終わっているでしょうから、抵抗力は従来よりも小規模になるでしょう。そうやって、あわよくば全滅させたい、そんな計画を練り、心にもない和平に合意したのではないか、とも考えられます。
そうなることが見えているから、ネタニヤフ首相は、トランプ大統領の顔を立て、和平に応じたのでしょう。汚職スキャンダル訴訟にしても、そうすぐに投獄されることはありません。裁判中に戦争再開になれば、再び戦時内閣として裁判を中断し、政権続投すればいいわけです。
このように考えれば、全て辻褄が合うのですが、和平が続くことを祈るばかりです。
* “Once Again, Israel Leaves Trump in the Dark as It Conducts a Military Attack”, New York Times, September 9, 2025.
https://www.nytimes.com/2025/09/09/us/politics/israel-trump-gaza-qatar-bombing.html
** “Why Trump’s pledge to defend Qatar is so extraordinary”, CNN, October 1, 2025.
https://edition.cnn.com/2025/10/01/politics/qatar-pledge-trump-analysis
吉川 由紀枝 ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
著書:「現代国際政治の全体像が分かる!〜世界史でゲームのルールを探る〜」
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
|
|
次 |
|