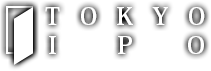東京IPO特別コラム:「不確実な時代の選択:インドの自立外交」
ここ数回「不確実な時代の選択」と題して、今後の日本の将来を考える上で参考になりそうな事例を取り上げてきました。今回はインドを取り上げてみたいと思います。
インドを巡る国際関係
インド外交の底流には、独立インドの初期に生まれた、米中の不信と、独立時からの双子の兄弟、パキスタンとの確執があります。これらをベースに、主にアメリカ、中国、パキスタンが動き、インドが反応する歴史が繰り返されています。その過程の中で、インドは、どの国にも依存しない一方、どの国とでも連携できるフリーハンドを常に模索する、自立外交を展開していると言えます。
独立後、インドはネルー首相の下、非同盟外交、東西陣営のいずれでもない「第三の道」を模索した姿が連想されやすいですが、実はそうでもありません。アメリカからの同盟関係を断ったインドは、アメリカがパキスタンと、相互防衛援助協定(MDA)という、準同盟ともいうべき軍事協定を結んだことに不信感を募らせます。こうした準同盟関係では、パキスタンは、最新ではないにせよ、アメリカ製新型兵器を輸入できることは簡単に想像できます。
そのため、インドはソ連に傾きます。冷戦期には、新型兵器の入手ルートは、米ソのいずれかの陣営からしかありません。そして、インドでは計画経済を導入し、パキスタンと武器や軍事技術面で負けないように、ソ連から輸入することになります。
また、インドとパキスタンの間では、冷戦期に3回戦争が発生していますが、その都度インドはソ連に頼り、インドに対する非難決議が可決されないよう根回しをし、ソ連が否決するのです。当然のことですが、国力の差が歴然としているパキスタンとの紛争に関し、インドは、インドとパキスタンの当事者のみでの解決を望み、パキスタンはそうはさせじと、紛争を国際問題化しようと画策します。
一方、中国に関しては、当初インドのネルー首相と中国の周恩来首相とが、「平和五原則」を提唱し、反植民地主義、平和共存等を訴え、1955年にはバンドン会議でアジアとアフリカ諸国による結束を呼び掛けており、関係は決して悪くありませんでした。
しかし、やがてイギリス植民地時代に設定されていた、中国とインド間の国境線について中国側が同意していなかったため、中華人民共和国政府もその立場を継承しました。さらに中国がチベットを併合し、チベット仏教の宗教的リーダーであるダライ・ラマ14世がインドへ亡命したこともあり、1962年には中印国境紛争が発生し、中国の圧勝に終わりました。しかし、これで国境問題が解決したわけではなく、国境を巡り、最近でも2020年に流血を伴う武力衝突が発生しています。
そうした緊張関係があれば、中国がパキスタンに接近するのは、理の当然です。孫子流に言えば、「遠交近攻」、中東流に言えば、「敵の敵は友」といったところでしょうか。ちょうどインドに振られたアメリカが、パキスタンに接近し、対してインドがソ連に接近するのと同じ論理です。
こうした経緯により、インドの対中、対米不信感はぬぐえません。そうした姿勢を反映してか、インドが定期的に首脳会議を行う相手国は、現在ロシアと日本のみと言います。*
目まぐるしい米中印間の駆け引き
とはいえ、ユーラシア大陸にあって、今時アメリカや中国と没交渉でやっていける国などありません。いくら中国並みの人口を抱え、経済ポテンシャルが大きく、2029年にはGDPが米中に次ぐ世界第3位(IMF見通し)になろうというインドであっても、です。
インドは、単体でアメリカや中国と対抗できるわけではありません。いずれかの国をけん制するには、他方の国と接近するしかありません。また、国益につながることであれば、積極的に接近する姿勢も見せます。例えば、近年以下のような外交が展開されました。
まず、中国の一帯一路政策には、複雑な行動を取ります。
海路については、2000年代、中国は中東から中国までの海上ルートが米海軍の制海権下にあることを懸念し、自らこのシーレーンを防衛できるよう、要所要所に自らの軍港を建設しようとしました。いわゆる「真珠の首飾り」作戦で、パキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントタ港、ミャンマーのチャウピュー港を自由に利用できるようにしています。
これは、インドからすれば、自国の庭のようなインド洋に中国海軍が頻繁に出入りするようになったことを意味し、それまでインドは強力な海軍を持つ必要性を感じていませんでしたが、ライバル視している中国の行動を見て、警戒心を募らせました。
こうした背景もあり、インドは、それまでの緩やかな組織体であった日米豪印間の戦略対話(クアッド)を、他メンバーの対中警戒心に共鳴し、2010年代後半に強化させ、「自由で開かれた」(意訳すれば、中国に独占的優位性を与えない)インド太平洋を強調することで、中国を4か国でけん制しようと団結します。
その一方で、陸路の方では、インドは一帯一路構想の一部である、中国パキスタン経済回廊(中国、パキスタン間の高速道路や鉄道等のインフラや、発電所等に中国が多額の投資を行う計画)に反対しました。理由は、印パ間で問題となっている国境のカシミール地方を通過するように予定されているからといいますが、中国の影響力がさらに高まることを懸念しているわけです。
しかし、その構想の要となるアジアインフラ投資銀行(AIIB)には、インドはちゃっかり加盟し、融資額は加盟国中で中国に次ぐ第2位であり、副総裁のポストを得ると共にAIIBの2017年融資先では、首位であったといいます。**
その後の2020年に再度、中印国境付近で軍事衝突が発生しました。すると、インドは中国に対し、TikTok等の中国製アプリを使用禁止にし、通信などの分野で中国企業の入札を禁止し、さらには中国製品のボイコットを呼びかけました。***とはいえ、インドにとり、中国は最大の貿易パートナーですので、深刻な影響は出ません。こちらもまた、抑制された反発です。
その後、第二次トランプ政権が始まり、米印関係は良好かと思われましたが、今年に入り、風向きが少々変わってきました。今年5月に印パ間で発生した武力衝突は、両軍の抑制により鎮火しましたが、これをトランプ大統領が自ら「仲裁」したと発表しました。印パ紛争を国際化させるような発言が、インドを激怒させたのは、いうまでもありません。
7月にはブラジルで開催されたBRICSサミット会議(このサミットに対し、トランプ大統領は不快感を示しています)にモディ首相が出席し、会議場では主役の習近平主席、プーチン大統領の不在の中、モディ首相の存在感が際立つ結果になりました。すると、8月にはウクライナ戦争の仕掛け人であるロシアから戦争継続資金を与えているとして、トランプ大統領は、インドのロシア産エネルギーや武器輸入を非難し、関税を50%に引き上げました。
そこで、8−9月に、2020年以来国境紛争により疎遠になっていた、中国の天津で開かれた上海協力機構(SCO)サミットに、モディ首相が出席し、緊張緩和が話題となりました。2度にわたる中ロへの接近の演出に刺激されたか、トランプ大統領の10月アジア歴訪中に、米印間で10年間の防衛協力枠組みが更新されました。元々、7,8月に更新予定でしたが、トランプ大統領による「仲裁」に不快感を持ったインド側が延期していたのでした。これにより、F35戦闘機等、アメリカ製兵器購入が可能になるとの見通しが立ち、その見返り?として、インドもアメリカ産エネルギー輸入に前向きな姿勢をみせるようになったと報じられています。****
自立外交はサスティナブルか?
インドは、なるべくアメリカにも、中国にも依存せず、適度に距離感を保ちつつ、できるだけ自立し、泣き所のパキスタン問題には他国に干渉されたくない、という外交方針を取り続けています。
もちろん、こうした外交はどの国にもできる芸当ではありません。インドのように経済ポテンシャルが大きく、地政学的に中国にも近く、対中包囲網を形成しようとする欧米の思惑に応えられるようなポジションにある一方、冷戦期にアメリカとの同盟を拒否し、独自色を貫こうとする強い意志と前科?もあります。
よって、1極が強大ではない、多極化の世界では、一つの地域大国として、他の大国も無視しえないポジションを持ち、誰とでも提携でき、提携を断ることができる、フレキシブルな外交は、ある意味理想かもしれません。(通常でしたら、米中双方から嫌われ、相手にされないでしょう。)
確かに、多国間のバランスを取り続けるのは難しいです。前述の通り、様々な国がそれぞれの思惑で動き、それらに適切にタイムリーに反応しなければなりませんし、それなりの図太さも必要です。ですが、それができるのであれば、国家存続の観点からは、良しとすべきでしょう。
但し、問題は、常に相手の思惑を理解し、自国利益最大化に向けて動き続ける、リアリストたちの無限闘争ループから自力では抜け出せない、すなわち、ポスト・多極化世界を切り拓く力はない、という点でしょう。
多極化世界は、常に物事が流動的で、力がよりモノを言い、弱い者の道理が通らず、そのはけ口がテロリズムのような暴力の形しかなくなり、より不安定かつ紛争が多くなることが予想されます。ですので、少なくとも初期の多極化世界の混乱期から安定期に向けて、革命的に新しい国際協調が、産まれなければなりません。現在の国連や傘下の国際機関が担うことは難しいかもしれませんが、そうした時代の先にも目を向けられる視野の広さ、新しいビジョンが必要なのではないでしょうか。そうでなければ、パラダイム・シフトが起き、ゲームのルールが変わった時、後手に回り、大負けするリスクがあります。
* 堀本武功著「インド 第三の大国へ」
** 堀本武功・村山真弓・三輪博樹編「これからのインド」
*** 熊谷 章太郎、「反中感情が高まるインドのジレンマ 〜容易ではない中国経済依存からの脱却〜」、日本総研ホームページ、2020年7月14日。
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/11947.pdf
**** “India-US sign 10-year defence pact amid tariff turmoil”, BBC, October 31, 2025.
https://www.bbc.com/news/articles/c5y0qz701xeo
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
著書:「現代国際政治の全体像が分かる!〜世界史でゲームのルールを探る〜」
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
インドを巡る国際関係
インド外交の底流には、独立インドの初期に生まれた、米中の不信と、独立時からの双子の兄弟、パキスタンとの確執があります。これらをベースに、主にアメリカ、中国、パキスタンが動き、インドが反応する歴史が繰り返されています。その過程の中で、インドは、どの国にも依存しない一方、どの国とでも連携できるフリーハンドを常に模索する、自立外交を展開していると言えます。
独立後、インドはネルー首相の下、非同盟外交、東西陣営のいずれでもない「第三の道」を模索した姿が連想されやすいですが、実はそうでもありません。アメリカからの同盟関係を断ったインドは、アメリカがパキスタンと、相互防衛援助協定(MDA)という、準同盟ともいうべき軍事協定を結んだことに不信感を募らせます。こうした準同盟関係では、パキスタンは、最新ではないにせよ、アメリカ製新型兵器を輸入できることは簡単に想像できます。
そのため、インドはソ連に傾きます。冷戦期には、新型兵器の入手ルートは、米ソのいずれかの陣営からしかありません。そして、インドでは計画経済を導入し、パキスタンと武器や軍事技術面で負けないように、ソ連から輸入することになります。
また、インドとパキスタンの間では、冷戦期に3回戦争が発生していますが、その都度インドはソ連に頼り、インドに対する非難決議が可決されないよう根回しをし、ソ連が否決するのです。当然のことですが、国力の差が歴然としているパキスタンとの紛争に関し、インドは、インドとパキスタンの当事者のみでの解決を望み、パキスタンはそうはさせじと、紛争を国際問題化しようと画策します。
一方、中国に関しては、当初インドのネルー首相と中国の周恩来首相とが、「平和五原則」を提唱し、反植民地主義、平和共存等を訴え、1955年にはバンドン会議でアジアとアフリカ諸国による結束を呼び掛けており、関係は決して悪くありませんでした。
しかし、やがてイギリス植民地時代に設定されていた、中国とインド間の国境線について中国側が同意していなかったため、中華人民共和国政府もその立場を継承しました。さらに中国がチベットを併合し、チベット仏教の宗教的リーダーであるダライ・ラマ14世がインドへ亡命したこともあり、1962年には中印国境紛争が発生し、中国の圧勝に終わりました。しかし、これで国境問題が解決したわけではなく、国境を巡り、最近でも2020年に流血を伴う武力衝突が発生しています。
そうした緊張関係があれば、中国がパキスタンに接近するのは、理の当然です。孫子流に言えば、「遠交近攻」、中東流に言えば、「敵の敵は友」といったところでしょうか。ちょうどインドに振られたアメリカが、パキスタンに接近し、対してインドがソ連に接近するのと同じ論理です。
こうした経緯により、インドの対中、対米不信感はぬぐえません。そうした姿勢を反映してか、インドが定期的に首脳会議を行う相手国は、現在ロシアと日本のみと言います。*
目まぐるしい米中印間の駆け引き
とはいえ、ユーラシア大陸にあって、今時アメリカや中国と没交渉でやっていける国などありません。いくら中国並みの人口を抱え、経済ポテンシャルが大きく、2029年にはGDPが米中に次ぐ世界第3位(IMF見通し)になろうというインドであっても、です。
インドは、単体でアメリカや中国と対抗できるわけではありません。いずれかの国をけん制するには、他方の国と接近するしかありません。また、国益につながることであれば、積極的に接近する姿勢も見せます。例えば、近年以下のような外交が展開されました。
まず、中国の一帯一路政策には、複雑な行動を取ります。
海路については、2000年代、中国は中東から中国までの海上ルートが米海軍の制海権下にあることを懸念し、自らこのシーレーンを防衛できるよう、要所要所に自らの軍港を建設しようとしました。いわゆる「真珠の首飾り」作戦で、パキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントタ港、ミャンマーのチャウピュー港を自由に利用できるようにしています。
これは、インドからすれば、自国の庭のようなインド洋に中国海軍が頻繁に出入りするようになったことを意味し、それまでインドは強力な海軍を持つ必要性を感じていませんでしたが、ライバル視している中国の行動を見て、警戒心を募らせました。
こうした背景もあり、インドは、それまでの緩やかな組織体であった日米豪印間の戦略対話(クアッド)を、他メンバーの対中警戒心に共鳴し、2010年代後半に強化させ、「自由で開かれた」(意訳すれば、中国に独占的優位性を与えない)インド太平洋を強調することで、中国を4か国でけん制しようと団結します。
その一方で、陸路の方では、インドは一帯一路構想の一部である、中国パキスタン経済回廊(中国、パキスタン間の高速道路や鉄道等のインフラや、発電所等に中国が多額の投資を行う計画)に反対しました。理由は、印パ間で問題となっている国境のカシミール地方を通過するように予定されているからといいますが、中国の影響力がさらに高まることを懸念しているわけです。
しかし、その構想の要となるアジアインフラ投資銀行(AIIB)には、インドはちゃっかり加盟し、融資額は加盟国中で中国に次ぐ第2位であり、副総裁のポストを得ると共にAIIBの2017年融資先では、首位であったといいます。**
その後の2020年に再度、中印国境付近で軍事衝突が発生しました。すると、インドは中国に対し、TikTok等の中国製アプリを使用禁止にし、通信などの分野で中国企業の入札を禁止し、さらには中国製品のボイコットを呼びかけました。***とはいえ、インドにとり、中国は最大の貿易パートナーですので、深刻な影響は出ません。こちらもまた、抑制された反発です。
その後、第二次トランプ政権が始まり、米印関係は良好かと思われましたが、今年に入り、風向きが少々変わってきました。今年5月に印パ間で発生した武力衝突は、両軍の抑制により鎮火しましたが、これをトランプ大統領が自ら「仲裁」したと発表しました。印パ紛争を国際化させるような発言が、インドを激怒させたのは、いうまでもありません。
7月にはブラジルで開催されたBRICSサミット会議(このサミットに対し、トランプ大統領は不快感を示しています)にモディ首相が出席し、会議場では主役の習近平主席、プーチン大統領の不在の中、モディ首相の存在感が際立つ結果になりました。すると、8月にはウクライナ戦争の仕掛け人であるロシアから戦争継続資金を与えているとして、トランプ大統領は、インドのロシア産エネルギーや武器輸入を非難し、関税を50%に引き上げました。
そこで、8−9月に、2020年以来国境紛争により疎遠になっていた、中国の天津で開かれた上海協力機構(SCO)サミットに、モディ首相が出席し、緊張緩和が話題となりました。2度にわたる中ロへの接近の演出に刺激されたか、トランプ大統領の10月アジア歴訪中に、米印間で10年間の防衛協力枠組みが更新されました。元々、7,8月に更新予定でしたが、トランプ大統領による「仲裁」に不快感を持ったインド側が延期していたのでした。これにより、F35戦闘機等、アメリカ製兵器購入が可能になるとの見通しが立ち、その見返り?として、インドもアメリカ産エネルギー輸入に前向きな姿勢をみせるようになったと報じられています。****
自立外交はサスティナブルか?
インドは、なるべくアメリカにも、中国にも依存せず、適度に距離感を保ちつつ、できるだけ自立し、泣き所のパキスタン問題には他国に干渉されたくない、という外交方針を取り続けています。
もちろん、こうした外交はどの国にもできる芸当ではありません。インドのように経済ポテンシャルが大きく、地政学的に中国にも近く、対中包囲網を形成しようとする欧米の思惑に応えられるようなポジションにある一方、冷戦期にアメリカとの同盟を拒否し、独自色を貫こうとする強い意志と前科?もあります。
よって、1極が強大ではない、多極化の世界では、一つの地域大国として、他の大国も無視しえないポジションを持ち、誰とでも提携でき、提携を断ることができる、フレキシブルな外交は、ある意味理想かもしれません。(通常でしたら、米中双方から嫌われ、相手にされないでしょう。)
確かに、多国間のバランスを取り続けるのは難しいです。前述の通り、様々な国がそれぞれの思惑で動き、それらに適切にタイムリーに反応しなければなりませんし、それなりの図太さも必要です。ですが、それができるのであれば、国家存続の観点からは、良しとすべきでしょう。
但し、問題は、常に相手の思惑を理解し、自国利益最大化に向けて動き続ける、リアリストたちの無限闘争ループから自力では抜け出せない、すなわち、ポスト・多極化世界を切り拓く力はない、という点でしょう。
多極化世界は、常に物事が流動的で、力がよりモノを言い、弱い者の道理が通らず、そのはけ口がテロリズムのような暴力の形しかなくなり、より不安定かつ紛争が多くなることが予想されます。ですので、少なくとも初期の多極化世界の混乱期から安定期に向けて、革命的に新しい国際協調が、産まれなければなりません。現在の国連や傘下の国際機関が担うことは難しいかもしれませんが、そうした時代の先にも目を向けられる視野の広さ、新しいビジョンが必要なのではないでしょうか。そうでなければ、パラダイム・シフトが起き、ゲームのルールが変わった時、後手に回り、大負けするリスクがあります。
* 堀本武功著「インド 第三の大国へ」
** 堀本武功・村山真弓・三輪博樹編「これからのインド」
*** 熊谷 章太郎、「反中感情が高まるインドのジレンマ 〜容易ではない中国経済依存からの脱却〜」、日本総研ホームページ、2020年7月14日。
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/11947.pdf
**** “India-US sign 10-year defence pact amid tariff turmoil”, BBC, October 31, 2025.
https://www.bbc.com/news/articles/c5y0qz701xeo
吉川 由紀枝???????????????????? ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
著書:「現代国際政治の全体像が分かる!〜世界史でゲームのルールを探る〜」
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665
|
|
次 |
|