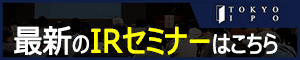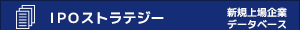現代中東を理解するための基礎知識
ここでは、イスラム世界の中でも中東、トルコ、イラン、エジプト(以後イスラム地域と呼びます)及びそのヨーロッパ移民を扱っていきます。
さて、日本人に馴染みの薄いイスラム地域を理解するのに、大事なキーポイントが2点あります。すなわち、この地域内での人口の大小と産油国か否かです。前者は、軍隊の大きさを、後者はその国の富を測る上での大まかな尺度となります。
大まかにいえば、人口が大きい国とは、イラン、イラクと東地中海沿岸にあるエジプトやトルコ、対して人口の小さい国とは、サウジアラビアを始めとするアラビア半島にある国々といえるでしょう。これまでの歴史の舞台は、文明の交差する東地中海沿岸が中心であり、砂漠中心のアラビア半島には紅海に抜けるイエメン以外にはほとんど注目は集まりませんでした。歴史に応じて人口が分布し、人口が大きいからこそ、ペルシャ帝国、古代エジプト帝国、オスマン・トルコ帝国等が誕生したと考えれば、納得感はあるのではないでしょうか。
一方、産油国とは、サウジアラビア、UAE、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート、イラン、イラクです。対して、非産油国は東地中海沿岸諸国が多く、トルコ、シリア、ヨルダン、イスラエル、レバノン、イエメン、(エジプト)です。新興富裕国として、産油国は20世紀後半からさらに発言力を持つようになり、それまで地域内での発言権が強かったエジプトやトルコよりも、サウジアラビアが浮上することになり、この事実からだけでも、昔から人口が大きく、かつ産油国であるイランと、そりが合わない下地があるように感じられるのではないでしょうか。
自立への道
旧オスマン帝国で最初に独立したのは、第一次世界大戦後のエジプトです。(元々19世紀にオスマン帝国から半独立したような状態でした)一方、旧オスマン・トルコ帝国は解体され、戦中の取り決め(サイクス・ピコ協定)通り、戦勝国のイギリス、フランスとの間で分割されました。この分割のロジックは、単に「英仏勢力圏の縄張りは、イギリスの資本投下が主として南部地域に、フランスの投資が北部地域に集中している現状を反映」*したからに外なりません。(但し、パレスチナは、連合国の利害関心が強すぎ、この際にいずれの国にも属さず、国際管理下に置かれたことから、悲劇が始まります。続きは後編で)
その後の第二次世界大戦により、英仏からの独立がかないましたが、アフリカと同様、独立当初はエジプト、イラン、シリア、ヨルダン、イラク等は親英派(イギリスの傀儡政権)でしたが、70年代末までにシリア、エジプト、イラク、イランで次々とクーデターが発生し、傀儡ではなくなっていきました。
傀儡政権からの脱却の次は、戦略資産の国有化です。始まりはエジプトでした。1952年ナセル大佐を中心とするクーデターが発生し、独立心の強い共和国となりました。これに危機感を抱いたアメリカ系アラムコが、自主的にサウジ側への利益分配額を増額し、サウジアラビアによる同社への課税を認めました。一方、イギリスではイランへの利益分配額を減額したため、イランの親英首相は暗殺され、反英派のモサデク首相が就任し、翌年アングロ・イラニアン石油会社の国有化を宣言しました。
これに対し、イギリスが世界中にイランの「一方的な」政策を非難し、イランからの石油輸入をしないようボイコットを呼びかけました。(当時石油タンカーを持つ国は限られていましたから、成功するかに思われましたが、唯一日本の出光興産が自前のタンカーを差し向け、格安で輸入したため、後の繁栄の基礎を築きました。)とはいえ、顧客1社だけでイラン経済が回るわけでもなく、1年足らずでCIAによるクーデターにより、モサデク政権はあえなく倒閣してしまいました。(但し、この報復はイラン革命で、親米派のシャーは国外亡命を余儀なくされました。)
さらに、エジプトは1956年スエズ運河国有化に踏み切りました。事の経緯は次の通りです。エジプトは、パレスチナ人奇襲部隊が行ったイスラエル攻撃を支持し、その中立主義外交から1956年5月に中華人民共和国を承認しました。これがアメリカの怒りをかき立て、エジプトの国家プロジェクトであったアスワン・ハイ・ダム建設への資金提供を停止しました。その報復措置として、ナセル大統領はスエズ運河国有化を宣言しました。これに反発した英仏が軍事介入しましたが、ソ連が英仏を非難したことにより、東西緊張が高まりました。冷戦真っただ中であったため、ソ連に資本主義陣営への非難の余地を与えてはならないと、アイゼンハワー政権が英仏に強力に圧力をかけ、撤退させました。
スエズ運河国有化の件で、すっかりアラブ界の雄となったナセル大統領が放った次の手は、汎アラブ主義でした。すなわち、元々アラブ民族は同じオスマン・トルコ帝国の民でしたから、欧米が作った国境を捨て、一つの国にまとまろうとアラブ連合結成を呼び掛けたのでした。同じく汎アラブ主義に傾倒していたシリアがこれに同意し、1958年から61年までアラブ連合共和国が誕生します。これに、北イエメンが加わりました。
しかし、心情的に汎アラブ主義に賛同しても、サウジアラビアのように自らの力で王国を建国した場合、そうたやすく国家主権を手放したくないのが、心情です。要は、一度国境が引かれ、その中で利害関係が定着すれば、大衆の心情よりも利得維持が大事ということです。
「アラブ主義の基礎とは、アラビア語話者間の親近感であり、それは中東では何よりも中核的な要素であり続けている。(中略)
アラブ統一に向けた努力が実を結ぶことは、ほとんどなかった。一般のアラブ人がどれほどパン・アラブ主義の大義へ情熱を燃やしていたとしても、いかなる国家機構に基づいてどのような統治が行われるべきなのかということについては、各国政府が合意に至ることは決してなかった。従って、アラブ連盟の創設から1960年代の一連のアラブ首脳会談に至るまでの初期段階ではいくつかの成功を収めたが、政治的統合も経済的統合も達成されることは無かった。
同じような分裂のプロセスは、石油の時代にも観察された。軍事的には強力であるが貧しい近隣アラブ諸国と産油国のあいだには、一見すると相互依存的な関係性を築くことが可能であると考えられた。というのも、産油国が喉から手が出るほど欲している労働力と軍事支援を、近隣アラブ諸国が石油収入の見返りとして供給することができるからである。
しかし、実際には産油国は独自の道を選択し、シリアやエジプトではなく米国やその同盟国から軍事的庇護を買い取ることを好んだ。事実、アラブ諸国は近隣諸国による介入の危険性を差し迫った脅威と考えており、それは協調関係からもたらされる利益への見込みを凌ぐものであった。それゆえ、アラブ統一に向けたいかなる計画も諸刃の剣であると考えられたのである。」**
むしろ、石油という利権の方が産油国を団結させています。1960年、サウジアラビア、イラン、クウェート、イラク、ベネズエラ間で石油輸出機構(OPEC)という石油カルテルが結成され、今日まで存続し、世界への影響力を定着させています。
イスラム主義
1979年、イランで親米シャー政権が倒され、ホメイニ師を指導者とするイラン共和国が誕生しました。これは、地域全体へ大きなインパクトを与えました。まず、冷戦のさなか、米ソ側に与しない、第三の道としてイスラム主義を挙げ、民衆の支持を得たことです。これは、民衆が汎アラブ主義、世俗主義に幻滅を感じ、イスラム主義に期待を寄せたことを意味します。
すなわち、汎アラブ主義ではアラブ諸政府の利害と衝突するので、実質的に実現不可能であり、世俗主義をトルコやエジプトで先駆的に追及したものの、近代化を急ぎすぎ、外国借款に依存した結果、欧米の大国に従属する羽目になってしまいました。この現状打破への希望が、イスラム主義なのです。
しかし、イスラム主義を無条件に政治に取り込むことは危険です。なぜなら、イスラエルとの実戦に向かわざるを得ないリスクがあり、過去4回の戦い(第一~四次中東戦争)で勝利のチャンスはないことを、アラブ諸政府はよくよく知っています。また、アラブ諸政府がイスラエルやその欧米同盟国と良好な関係を保ち、サウジアラビアのようにアメリカに米軍基地を提供している国さえありますから、反欧米感情とイスラム教が結びつくと、制御不能なまでの暴力に発展し、矛先がアラブ諸政府にまで向けられ、政権打倒に至るリスクさえあります。
そのため、アラブ諸政府は民主化にも、イスラム政党の認可にも、非常に消極的です。(十字軍時代、約100年キリスト教徒国家があったため、現在でもマロン派キリスト教徒が多い)レバノンを除けば、イスラム教徒が大多数ですから、イスラム法(シャリーア)に基づく社会体制を求める多数の声を、止めるわけにはいかなくなります。加えて、ムスリム同胞団、ヒズボラ等元々は草の根運動から大きくなったことからも分かるように、イスラム団体はゴミ収集を始め政府が行き届かないサービスをボランティア的に展開することによって、民衆の支持を獲得することに、非常に長けています。いざ民主化するとなれば、官製政党等よりも遥かに高い人気を想定せざるを得ないのです。
そして、これに気付いている欧米政府も、民衆の民主化を求める声には賛同しますが、イスラム政党の勝利には否定的になので、民主化を支援する行為はしません。事実、「エジプトでは、1923年から1952年の間に総選挙が10回実施され、そのほぼ全てでワフド党が国民の支持を受けて勝利したのに、わずか5回しか政権を担当できなかった。決まってイギリスやエジプト国王に下野を強要されたからだ。」***アラブ諸国の民衆は、これをダブルスタンダードとして非難します。
イラン革命の2番目のインパクトとして、イラン・イラク戦争、ソ連のアフガニスタン侵攻、ひいては湾岸戦争を引き起こしたという点です。イラン革命は、上記の理由によりアラブ諸政府に危機感を与えました。しかし、人口の大きいイラン国軍に対し、匹敵する大きな軍隊を持つ国は、地域内では非常に少ないです。そこで、イラン革命中将校の多くが粛清されたことに着目した隣国イラクが、アラブ諸政府の「防波堤」として、またイラン革命の輸出を恐れたアメリカの支援を受け、イランに侵攻したのでした。また、同様にイラン革命の輸出を恐れたソ連も、隣国アフガニスタンの共和党政権を支援すべく軍事介入し、双方とも10年近い泥沼戦争にはまり、明確な勝利を誰も手にすることのないままに終わったのでした。
そして、イラン・イラク戦争時、アラブ諸政府はイラク政府に資金援助していたのですが、イラク政府としては返済義務がない義援金と理解していました。しかし、クウェートだけが、返済を求めました。ただでさえ、イラクは戦後復興にお金がかかります。さらに、戦後復興費捻出のため石油を高く売りたいところを、クウェートが石油を値下げしてしまいました。この2点にイラクが激怒し、クウェートへ侵攻してしまいました。
最後のイラン革命のインパクトは、イラン革命以降イスラム教の権威ではない人々が、誤ってイスラムを解釈し、イスラム主義を煽っていくという傾向が生まれた点です。あまり知られていませんが、イラン革命の指導者、ホメイニ師自身、それほど高いイスラム教の学識を持った人物ではありません。革命後イスラム法の解釈に関しては、ホメイニ師も持論をイスラムの最高指導者層に押し付けられなかったと言われています。
オスマン・トルコ帝国の凋落時代から、イスラム社会で近代化や西洋化にどう社会が立ち向かうべきかを議論していたのは、イスラム教の学識者たちでした。しかし、イスラム世界が西洋に立ち遅れた責任を押し付けられ、次第にその権威が薄れていったわけですが、ここに至ってイスラム教の本質からかなり逸脱したところまで来てしまっています。その系譜は、今日ではタリバン、イスラム国家(IS)等の組織に引き継がれています。
例えば、「クルアーンは、宗教上の問題について力を強制することには断固反対しており、その見解は―排他と分離を解くのではなく―寛容で他者を排除しないものだった。しかし、クトゥブ(「イスラム原理主義の創始者」と呼ばれる)は、「クルアーンの説く寛容は、イスラームが政治的に勝利して真のイスラーム国家が樹立された後にのみ求められると主張した。(中略)イスラーム法は、ムスリムが自分の選んだ宗教を自由に進行できる国に宣戦布告することを禁じているし、罪のない民間人を殺すことは厳禁している。原理主義的見解の仲介にある不安と怒りは、原理主義者が守ろうとしている伝統をほとんど常に歪めてしまう傾向があ」ります。***
学識がある人が、弁舌に長けているとは限りません。今日インターネット等で簡単に情報が拡散されますが、そこに情報の真偽をチェックする機能はありません。現状に不満を持った若者が、たまたま接した、耳に心地よい説教を信じ込んでも不思議ではありません。(事実ロックスター並みに人気な「イマーム」がいるようです)
そして、「イスラム原理主義」と言われる過激派組織が描く、コーランを都合よく解釈した世界を信じ、指示されるままに自爆テロ等の戦士になっていく現象が増えています。このような若者は、イスラム地域のみならず、1950-70年代前半の間、西ドイツやフランス等で移民労働者として受け入れられたイスラム系移民の第三世代にも多いと言われています。
この世代は、親の世代と異なり、移民先の学校に通い、移民先の言語も流暢であり、現地社会の一員である認識を持っているにも関わらず、周囲からは移民の子という偏見の眼で見られ、居心地の悪さを抱えている場合が多いです。そんな心の隙間を、過激派組織は付け込みます。(コーランの原典を読めば、嘘か本当かわかるはずと思いたいところですが、コーランは他言語では正確に訳せないと、アラビア語が主流である一方、移民三世はすでにアラビア語が読めないので、真偽を質しにくいということもあるようです)
*奈良本英佑著 「パレスチナの歴史」
**ロジャー・オーウェン著 「現代中東の国家・権力・政治」
***カレン・アームストロング著 「イスラームの歴史」
吉川 由紀枝 ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665