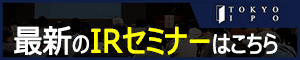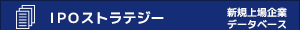パレスチナ問題の起源
パレスチナ問題のそもそもの発端は、第一次世界大戦中のイギリスの三枚舌外交のせい、と言われます。3枚の舌の1枚目は、イギリスはフランスとオスマン・トルコ帝国解体後の領土分割を協議し結んだ、サイクス・ピコ協定です。以前お話しました通り、英仏の資本の集中投下場所に応じて、中東の南部をイギリスが、北部をフランスが、その勢力下に持つことになりました。その一方、パレスチナは国際委任統治となりました。理由は、「パレスチナがユダヤ教、イスラム教、キリスト教諸宗派共通の聖地であり、連合国の各々が強い利害関心を持っていたからだ。連合国相互の協調体制を維持するためには、そこをどこか1つの国に委ねることはできなかった。」*
2枚目は、バルフォア英外務大臣がイギリス・ロスチャイルド家に書いた一筆、いわゆるバルフォア宣言です。すなわち、第一次世界大戦中英首相が、ロスチャイルド家に戦時国債の大量購入を依頼しました。その際に担保は何かと問われ、「イギリス帝国」と答え、ロスチャイルド家がその依頼に応じたことは有名ですが、その担保行使の一環?として、誕生したのが、パレスチナにユダヤ人国家の建設を支援するという、この一筆でした。
ロスチャイルド家がこうした依頼を出した背景には、1920年代から巻き起こったシオニスト運動があります。日露戦争中ロシア帝国が行ったポグロム(ユダヤ人虐殺)等を始め、ヨーロッパ内でのユダヤ人への迫害から逃げるため、先祖の地シオン(現パレスチナ)にユダヤ人が安心・安全に暮らせる国を求める声が強くなりました。とはいえ、パレスチナから遠く離れた人々にとり、その地には既に他の住民がいる想定であったかは、定かではありません。
一方、既にイギリス貴族社会に根を下ろしているロスチャイルド家にすれば、今さらユダヤ人への人種差別問題をことさら大きくしたくなかったでしょう。ですが、イギリス政府がシオニストを支援する「一番大きな動機は、スエズ運河と至近距離にあることを含めた、この土地の戦略的位置を重視」したことにありましたので、ロスチャイルド家に花を持たせる形で、シオニストの意見が通ることになりました。
3枚目は、「アラビアのロレンス」こと、T.E.ロレンス英情報将校が、アラブ人に対し、オスマン・トルコ帝国への反乱と引き換えにアラブ国家樹立を約束したというものです。それでも、まだ第一次世界大戦後、当初はロレンスを支援したハシム家を傀儡政権として、イギリスがアラビア半島、トランス・ヨルダン、イラクにそれぞれ王国を樹立した当初は、まだよかったのです。
しかし、ナチスドイツの反ユダヤ政策により、ユダヤ移民数は増えていきました。「1945年当時、パレスチナの総人口は約177万人、うちユダヤ人口は約58万人と推定」*されています。これらのユダヤ人は近代的な教育や技術を持ち、農業に最適な土地や水利の面等戦略的な要衝地を真っ先に購入し、農業等に従事しますので、生産力でも現地民と比べ、6-15倍の差があったと言われています。
一方パレスチナでは、第二次世界大戦ブームにより都市労働者への需要が高まり、10万人以上のアラブ人労働者が集まっていました。しかし、「戦争ブームが去った時、職を失った大多数のアラブ人労働者は、社会保障もないまま、出身の農村にも帰れず、(中略)都市部に残り、スラムを形成する。」*
こうした事態に、イギリス政府はようやくアラブ人の失業が深刻であり、ユダヤ移民の数と土地売買の制限が必要と認識しました。しかし、時はすでに遅し。シオニストはイギリス議会へのロビー力を付け、現地の安定に必要な規制を出せませんでした。
結果、行き詰まったイギリス政府はアメリカの支援を求めますが、アメリカ政界でもシオニストのロビー力が強く、両政府はなす術もなく、国連にこの問題を委ねます。そこでシオニストに有利な形で、英軍は撤退し、その後ユダヤ国家とパレスチナ国家が誕生するという内容が決議されました。
この決議を引き出したシオニストたちは、英軍撤退と同時にイスラエルを建国すべく、また周囲のアラブ諸国から攻撃を受けることを予想し、可能な限り欧米から武器を密輸し、綿密な準備をしました。(当時は第二次世界大戦で使用済みの中古武器が沢山ありました)
一方、想定外のユダヤ人国家の誕生に、アラブ側の対応は目も当てられませんでした。「アラブ諸国には、統一された戦争目的も政治目的もなく、作戦を調整する統合司令部もなかった。また、実戦経験を積み、まともな訓練を受けていたのは、トランス・ヨルダンのアラブ軍団(後にヨルダン王国軍)だけ。ところが、このアラブ唯一の精鋭部隊は、イギリス人将校の指揮下にあり、イギリスの政治的判断によってその活動を制約されていた。アラブでは最大規模のエジプト軍は、司令官たちが準備不足を理由に参戦に反対したのだが、ファルーク国王の命令で急遽出動していた。このようにしてパレスチナへ送られた各国軍はそれぞれの個別利害によって行動した。例えば、アラブ軍団は、『アラブ国』予定地の西岸地区と聖地エルサレムの確保にほぼ専念した。アブドゥッラーとシオニストの秘密合意で、パレスチナを分け合うことになっていたからだ。エジプト軍は、ガッザから海岸沿いに北上、一挙にテル・アヴィヴを突いて撃退された。イラク軍は、同国の油田と地中海を繋ぐ石油パイプラインの出口にあたるハイファ―を狙って阻止された。」*
結局各国軍を個別撃破したイスラエルは、それぞれと休戦条約を結び、第一次中東戦争が終結しました。そして、戦勝国イスラエルが支配下においた領土は、パレスチナ全土の約77%となり、残りの23%(エルサレム東部を含むヨルダン川西岸地区とガザ地区)は、それぞれトランス・ヨルダンとエジプトの支配下に置かることとなりました。これが実質的なイスラエルの国境となったのです。
さて、周囲を敵に囲まれる覚悟で建国したイスラエルをどう捉えるべきでしょうか?中東学者の酒井啓子教授は、次のように当事者の言い分を説明しています。「イスラエル側は、パレスチナ人を追い出したことの不当性を真っ向から否定する。『パレスチナ人』とは、パレスチナに住む、民族的にはアラビア語を話すアラブ民族の人々である。アラブ民族はシリアやヨルダンや、他の国にたくさんいるのだから、パレスチナに住まなくとも他のアラブ民族の住む地でアラブ民族として生活すればいいではないか。『パレスチナ人』という固有のアイデンティティを持つ人々等、存在しない。こうした発想が、イスラエルの政治家の間で長く根付いてきた。
一方で、アラブ諸国は、ユダヤ人を規定しているのはそもそも宗教であって、『民族』ではないのだから、ユダヤ教徒だけ集めて国民とする発想はおかしい、と考える。オスマン帝国時代まで、ユダヤ教徒はイスラーム教徒と共存してきたのだから、アラブ地域にいるユダヤ教徒は、そのままアラブ民族のユダヤ教徒として生きればいいではないか。ドイツにいたユダヤ教徒は、ドイツでユダヤ教徒のドイツ人として生きればいいではないか。イスラエルの建国は、西欧のアラブ地域に対する植民地支配の一環に他ならない。」**
中世から近代においても、スペインがレコンキスタ運動の結果、イベリア半島をイスラム教徒からキリスト教徒のものに奪還した後、かの地に在住していたユダヤ人は改宗か国外移住を迫られました。その際ユダヤ人が多く向かった先はイタリアですが、中東にも安住の地を求めましたし、イスラム教徒は彼らを受け入れました。(ムハンマドの時代からユダヤ教徒やキリスト教徒が存在していたので、共存の道を示していましたから。)普通にユダヤ人もイスラム教徒も良き隣人でした。1949年エルサレム郊外のアラブ村デイル・ヤーシンでイスラエル軍が、無辜の村民を虐殺するまでは。
確かに、ユダヤ人をナチスドイツが迫害し、その過酷さを第二次世界大戦終結直前まで見て見ぬふりをした欧米連合国に対し、ユダヤ人が非難する権利は十二分にあります。それでも、全く関係ないパレスチナの人々を追い出す権利はありません。それでも、被害者が他の弱者に対し簡単に加害者になってしまう事例は、悲しいことにこれが最初でも最後でもないでしょう。
第三次中東戦争後に目覚めたパレスチナ人
第二、三次中東戦争でイスラエルがアラブ諸国に圧勝した結果、パレスチナ全土にシナイ半島、ゴラン高原をも抱えた、中東の超大国となりました。結果、アメリカは中東の重要な戦略拠点として、イスラエルを最大の武器供与国にしましたし、第三次中東戦争の最中に獲得したと言われる、核兵器保有も容認してきました。
当然冷戦時ですから、アメリカがイスラエル側につけば、ソ連がエジプト、シリア、イラク等ナショナリズム急進派の諸共和国に接近するわけで、その間で「ヨルダンやサウジアラビアなど保守的な君主国は、親米・親西欧政策を取りつつイスラエルと対決するという、微妙な立場に置かれることになった。」*
一方、「エジプト、シリア、ヨルダンの三国は徹底的に叩きのめされ、アラブ・ナショナリズムが求めた民族の統一は夢と消えた。そして、敗れた三国だけでなくいずれのアラブ諸国も自国だけの国益を、あからさまに追及することになった。この戦争に『解放戦争』の期待をかけたパレスチナ人たちが、もはやアラブの統一も、アラブ諸国からの政治的・軍事的支援も、あてにすることはできないことを思い知らされた。」*
そうした背景で名をはせたのが、パレスチナ人による、パレスチナ解放機構(PLO)です。第三次中東戦争の翌年、PLO率いるゲリラ隊がイスラエル正規軍と衝突し、イスラエルへ大きな損害をもたらしました。多少なりとも第三次中東戦争の敗北に対する溜飲が下がったとして、アラブ界では一目置かれる存在となったPLOは、その後レバノン政府間で「カイロ協定」を結び、難民キャンプの自治や一定の条件のもとでのゲリラの活動を認められるようになりました。
こうした流れの中、PLOは「武装闘争によるパレスチナ全土の解放」から「パレスチナ問題の政治的解決」へと方向転換し、アラブ界のみならず西欧へも積極外交を展開していくようになりました。その甲斐あって、PLOは1974年国連でオブザーバー席を獲得するまでになりました。
しかし、1970年にはPLOの人気を警戒した親欧米ヨルダン政府との戦闘(ヨルダン内戦)が始まり、1973年第四次中東戦争の結果***、エジプトはイスラエルと国交樹立してしまいました。さらに、1975年のレバノン内乱(レバノン内のキリスト教徒対イスラム・PLO連合に乗じてシリア、イスラエルが介入。以後イスラエルはレバノンとの国境地帯を間接支配)により、イスラエルと国境を接する両国での活動拠点のみならず、政治・軍事・社会組織を支えてきた基盤が破壊されてしまい、1982年PLO指導部はモロッコへの逃走を余儀なくされました。
一方、PLO指導部は逃げられても、パレスチナ・アラブ人の庶民はそうはいきません。そこで始まったのが、第一次インティファーダ(草の根の抵抗運動)です。ガザのイスラエル軍とパレスチナ人労働者との間の交通事故を契機に、パレスチナ人が抗議デモ化し、すぐにパレスチナ全土に広がったのでした。
ここで少々解説が必要ですが、パレスチナではイスラエルのユダヤ人がどんどん入り込み、生活を営み始めます。(入植)元々いたパレスチナ・アラブの人々は家を壊され、畑を潰され、追い出されます。当然これはイスラエル政府が了承していることなので、パレスチナ・アラブ人には抗議を聞いてくれる機関はありません。そこで、ユダヤ人に入植されていない土地にとりあえず避難し、そこからユダヤ人の作った都市へ出勤し、低賃金労働に従事することを余儀なくされます。これは、アフリカの植民地化で使われた手口と全く同じです。(2000年頃、ユダヤ人とパレスチナ・アラブ人の平均年収格差は3倍程度と聞きました)このようにユダヤ人がやりたい放題に入植するため、パレスチナでアラブ人が住める土地はどんどん蚕食され、スポンジの穴のように、「陸の孤島」化されていきます。
そこに、1990年イラクがクウェート侵攻(湾岸戦争)し、世界からの非難に対し、イラクはリンケージ理論を持ちだしました。すなわち、イスラエルも本来パレスチナ国家であるべき領土から大きく逸脱して西岸・ガザ地区を占領しているのだから、イスラエル軍の撤退と同時にイラク軍の撤退を行うべきと主張したのでした。イラクの都合で作り上げた屁理屈であることを承知していたでしょうが、これに大きく心をゆすぶられたPLOは、表立ったイラク非難を控えたために、「『イラク支持』のレッテルを貼られ、アメリカだけでなく、ヨーロッパでも世論の支持を失ったのだ。さらに、ペルシャ湾岸の豊かな産油国からは、PLOへの資金援助を止められ、クウェートや周辺の産油国で働くパレスチナ人の専門家や労働者が集団で追放された。」*
湾岸戦争によりアラブ界からの同情を失ったことと、ソ連崩壊によるパレスチナへの軍事支援停止が、PLOへの大打撃となり、PLOアラファト議長曰く、「湾岸戦争直後PLOの年収合計は、前年の3億ドルから、4000万ドルに激減した」*。
一方のアメリカも、このようにパレスチナ問題を取り上げられたら、何かしら動かないといけないという道義的な義務を突きつけられた格好となりました。ましてや、時は冷戦直後の、世界的に平和への期待が高まっていた時代です。
そこで生まれたのが、クリントン政権下のオスロ合意とキャンプ・デービッド交渉です。前者は、PLOをパレスチナ自治政府(PA)としてイスラエルが承認する代わりに、今後5年間で相互の領土について交渉することであり、後者はパレスチナ・アラブ側のゲリラ行為、インティファーダを含む、イスラエルへの暴力をすべて放棄し、多少の領土の交換はあっても陸の孤島状態は変わらないというものでした。後者についてはあまりのパレスチナ側への不利さから、さすがにPLOが拒否しました。
不幸にして、この交渉直後のイスラエル総選挙で、強硬派のリクード党が返り咲き、第五次中東戦争を率いたシャロン将軍が首相となり、「もはや自制しない」と宣言し、入植、攻撃を激化させていきました。対して、パレスチナ側は、強硬派のハマス主導の第二次インティファーダで応じるようになりました。そして、アラファト議長が死去した後の2006年PA総選挙で、ハマスがPAで政権を担い続けています。
こうして両サイドとも強硬派という不幸な組み合わせのまま、暴力の連鎖反応が今日に至るまで、断続的に続いています。そして今月発生したパレスチナでの紛争も、この一環として理解できます。特に、近年アラブ諸国はイスラエルと国交樹立してきています。今まで見てきました通り、内実自国の利益優先で行動していますが、少なくとも表面的には親パレスチナの態度をとってきたアラブ諸国が露骨にイスラエル側に付くのではないか、パレスチナ問題を政治アジェンダに乗せる国がなくなるのではないかという焦燥感から、今回の紛争が発生したと解釈できます。そして、アラブ諸国は反対しないと踏んだのか、イスラエルはこの機に乗じて、パレスチナ人を全員虐殺か追放することでパレスチナ問題を解決しようと企んでいるのではないかと思われるほどの軍事作戦を展開しつつあります。
*奈良本英佑著 「パレスチナの歴史」
**酒井啓子著 「中東の考え方」
***第四次中東戦争で、ナセル大統領の後継者・サダト大統領率いるエジプトが、イスラエルに電撃攻撃を仕掛け、シナイ半島を取り戻しました。ここまではよかったのですが、エジプトは緒戦の勝利を政治的な成果にしなければなりません。長期化させれば、アメリカがイスラエルを軍事支援するわけですから、勝ち目はありません。この時点であまりエジプトに交渉力がなく、結局イスラエルのペースのままパレスチナ問題で何ら合意できず、シナイ半島をエジプトに返還する代わりにイスラエルと単独和睦、すなわち単独国交樹立しました。これで、エジプトは中東アラブ諸国内では「裏切者」になってしまいました。
吉川 由紀枝 ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665