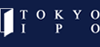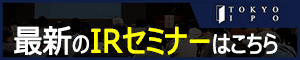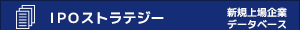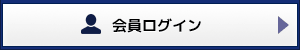6月13日イスラエルによるイランへの直接攻撃が起きるまでは、外交でイラン核問題を解決する方向で動いていたトランプ大統領が、一転21日イラン核施設爆撃に踏み切りました。まずはその理由を探っていきましょう。
なぜアメリカも参戦したか?
もともと、トランプ大統領の支持基盤も、この件に関しては二分していました。アメリカ再建を最重視するMAGA派は、いつとも果てぬイスラエルとイランとの戦いに介入し、アメリカを再び泥沼の戦いに巻き込むな、アメリカ再建が最重要課題であると主張します。
一方、親イスラエル派は、イスラエルと共に攻撃に参加すべきだといいます。特に、イラン核施設が地下にもあり、イスラエル軍では地上施設しか破壊できず、地下施設まで破壊するには、アメリカ軍しか保有していない「バンクバスター」爆弾しかないと言われていました。ですので、イスラエルとしては是が非でも、それを使用したかったわけです。
両者が拮抗し、いずれにトランプ大統領が傾くか、トランプ大統領が決断するまで、誰も分かりませんでした。いずれ、さらに検証記事が出てくるのでしょうが、今までの報道によれば、トランプ大統領は国家安全保障会議(通称NSC)上、「エスカレーションを招かずに、イラン核施設を破壊することは可能」と聞かされたとのことです。*この回答が、トランプ大統領の背中を押したのでしょう。
アメリカ参戦が抱えるリスク
1)エスカレーションが本当にない保証はない
アメリカがイランを攻撃しても、イランからのエスカレーション(報復措置)を招かないという前提は、非常に疑問です。米軍はサウジアラビアやカタール等中東に米軍施設を持っていますから、イランはその気になればこれらの米軍基地や近辺を航海中の海軍船舶を攻撃できます。
実際23日にカタールの米軍基地が標的になり、ミサイル防衛システムで撃墜できました。今回はイラン政府によるカタール政府への事前通知があったため、迎撃はまだ容易だったでしょうが、今後被害が出た時、トランプ大統領は自制できるのでしょうか?自制できなければ、イランからの攻撃は続きますし、反撃すれば、全面戦争となり、泥沼戦争になります。
確かに、イスラエルがイランへ攻撃を1週間以上続けていますが、イランからの反撃は予想に反して被害が小さく収まっています。特に超音速ミサイルを発射したと言われていますが、事前に恐れられていたほどの威力を見せませんでした。この理由を、イラン革命軍の腐敗が激しいからだと分析する専門家もいるくらいです。
しかし、イランはアメリカや他国を巻き込まないように配慮した上で攻撃していたと考えられます。特に、米兵がたまたまイスラエル軍基地内にいたとなれば、イランがアメリカを巻き込んだと言われかねません。故に、簡単にイランがアメリカに対し、エスカレーションしないと言い切ることは、不誠実でしょう。
2)ホルムズ海峡閉鎖によるオイルショック再発も
加えて、イランは、目の前のペルシャ湾で最も狭いホルムズ海峡を封鎖することも可能です。世界の石油の4割がここを通ると言われているところですから、世界中でオイルショック再発は確実です。既にこのリスクが指摘されているだけに、産油国カルテルともいうべきOPECでは、緩やかな増産を目指すと言っていますが、すぐには対応できません。よって、世界中の石油供給が減少し、当然石油価格が高騰します。アメリカ再建を謳うトランプ政権には、支持層の生活へ大きな痛手を与えることができます。この影響は、日本にとっても重大です。(古々々々米の値段で騒いでいる場合ではありません。)
3)核拡散が勢いづく
なぜイランが攻撃され、なぜインド・パキスタンが全面戦争を自制し合ったか?と問う人々は多いでしょう。多くが出す結論は、核兵器の有無となります。今までイランはIAEAや米欧との交渉結果を遵守し、核兵器を「まだ」開発していませんでした。
故に、米欧と友好関係がなく、外交で戦争回避を考えていた国々は、その考えを改め、自衛のため核武装すべきだという結論に至ってもおかしくありません。特に北朝鮮の金正恩総書記は、IAEAの言うこと等聞かずに核武装していてよかったと、胸をなでおろしていることでしょう。
4)政変(レジーム・チェンジ)は親米政権を作らないし、金食い虫になるだけ
仮に、このままイランが本格的な攻撃ができず、現行政府が機能不全になったとしましょう。その場合、イラク戦争後のイラク同様、アメリカはイスラエルに協力し、イラン国内に多国籍軍を送り、しばらく軍政を敷くことが考えられます。(無政府状態の焼け野原で放置すれば、あっという間にテロの温床となります。)軍政とは、とどのつまり、一国分の政府機能をある程度外国から持ってくることですから、地元民の協力次第で必要なコストが変動します。
そしてこの場合、イラク戦争後のイラクよりも、割高を覚悟せねばなりません。イラクの場合、まだサダム・フセイン率いるバース党の圧政に苦しんだイラク国民がいたので、当初は歓迎されました。しかし今回、IAEAに加盟もせず国際社会の暗黙の了解で核兵器を保有するイスラエルが、IAEA規定に遵守していたイランを攻撃するという「理不尽」がまかり通り、これに仲介者の顔をしていたアメリカが攻撃に加わったため、両国への怒りが、イラン国民を結束させてしまっているからです。
加えて、イスラエル主導で動くのも難しいでしょう。イスラエルの人口は、たかだか1000万未満です。しかも、約200万のガザ市民と共存することもできずに持て余した結果、抹殺しようとしている国民ですから、約9000万人を抱えるイラン等まともに対処できないでしょうし、アメリカに丸投げするだけでしょう。
それでも軍政を敷いている間は、米イスラエル軍がテロ行為を直接押さえつけることは出来ます。しかし、いずれ軍政にかかるコストがアメリカ国内で問題となり、現地政府へと移行せざるを得なくなります。その場合、世俗政府(ハメイニ師という宗教をベースにした国家元首ではなく、国民が選出した人物を国家元首にする)を条件にしても、イラン国民に投票させれば、反米イスラエル政府になることは確実です。ですので、安易に軍政を解除もできません。
よって、アメリカがすべてのツケを払う形になり、最悪な泥沼です。
起死回生の秘策を切れるか?
事ここに至って考えられる起死回生案が、一つあります。それは、今回の爆撃により、アメリカがイランの核兵器開発能力のなさを「証明」したとして、現行政権の温存を許し、対イラン経済制裁を解除することです。ここで今までの米イラン交渉(イラン核武装放棄と対イラン経済制裁解除の取引)を決着させます。さらに、イスラエルの攻撃を止めさせ、イランの安全保障を与える代償として、に引き続きIAEA査察を受け入れるよう、イラン政権と取引することです。
もちろん、イスラエルはこの機に乗じて、さらに攻撃を継続したいというでしょう。しかし、そこを押さえられるか否かで、トランプ大統領がイスラエルの傀儡か否かを見極めるポイントになります。いざとなれば、ネタニヤフ首相をアメリカに呼んで国際刑事裁判所(ICC)に引き渡せばいいのではないでしょうか?ある意味、喧嘩両成敗ですし、近隣アラブ諸国にも多少納得感があるのではないでしょうか。その方がガザ虐殺を止める近道になるでしょうし、トランプ大統領の念願である、イスラエルとアラブ諸国との国交樹立、そしてノーベル平和賞受賞への道が開けるというものです。
「誰も自分が何をするか分からない」と豪語できる大統領にしかできない荒業ではありますが。。。
* “US joins Israel in attacking Iran, strikes Fordow, Isfahan, Natanz sites”, Al Jazeera, June 22, 2025.
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/22/us-joins-israel-in-attacks-against-iran-strikes-key-nuclear-sites
吉川 由紀枝 ライシャワーセンター アジャンクトフェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所
にて通信・放送業界の顧客管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ビジティングリサーチ
アソシエイト、上級研究員をへて2011年1月より現職。また、2012-14年に沖縄県知事
公室地域安全政策課に招聘され、普天間飛行場移転問題、グローバル人材育成政策立案に携わる。
著書:「現代国際政治の全体像が分かる!~世界史でゲームのルールを探る~」
定期購読はこちらからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001693665